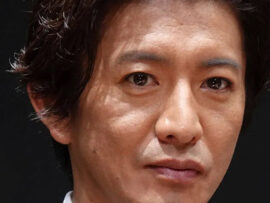7月20日に投開票が予定されている参議院選挙において、最も注目される争点の一つが「物価高対策」です。与党である自民党と公明党は、国民一人当たり2万円の給付案を提示しています。これに対し、多くの野党は消費税の減税を公約に掲げています。今回の選挙は、もしかすると政権の枠組みに変化をもたらす可能性も指摘されています。自公両党の勝敗ラインは改選50議席とされていますが、「給付」か「消費減税」かという対立軸での審判が下される中で、本質的な議論が見過ごされてしまう危険性もはらんでいます。
 石破茂首相の選挙活動中の様子
石破茂首相の選挙活動中の様子
与野党の物価高対策の対立点
自民党は国民一人当たり2万円の給付を打ち出し、物価高による国民生活への影響を和らげるとしています。一方、野党各党は消費税減税を主要な物価高対策として提案しています。例えば、立憲民主党は来年4月から食料品の消費税を1年間ゼロとする案を掲げ、経済状況に応じて1回の延長を可能とする方針です。これにより年間5兆円、国民一人当たり約4万円の負担軽減効果があると試算しています。日本維新の会も2年間限定で食料品の消費税を0%にすることを提案しており、れいわ新選組は消費税そのものの廃止を主張しています。
国民民主党は消費税率を10%から5%への減税を訴え、賃金上昇率が物価上昇率に2%を上回るまで継続する意向を示しています。厚生労働省が7月7日に発表した5月の実質賃金は5ヶ月連続のマイナスとなっており、現状では賃金上昇が物価高に全く追いついていない状況です。共産党は消費税廃止を究極の目標としつつ、緊急措置として税率を5%へ引き下げる減税策を直ちに実施すべきだと主張しています。食料品のみの減税や期間限定では不十分であり、物価高対策として最も有効なのは、あらゆる商品・サービスにかかる消費税負担を減らすことだと強調しています。
財源論と議論の本質
これらの消費税減税案に対し、石破茂首相は7月1日の党首討論で、「消費税は大切な社会保障の財源です」と述べ、減税の財源確保の難しさを指摘しました。しかし、立憲民主党は基金の活用、国民民主党は税収の上振れと国債発行など、野党各党はそれぞれ財源に関する提案を行っています。そのため、財源論だけで減税案を退けるのは難しい状況です。与党側がより深く議論すべき点としては、「消費税減税が国民の負担軽減策として本当に効果的に機能するのか」という点が挙げられます。単に減税すれば良いというわけではなく、その実効性についても検証が必要です。

今回の参議院選挙では、物価高対策として与党の「給付」と野党の「消費税減税」という分かりやすい対立軸が提示されています。しかし、この二項対立の議論に終始するのではなく、それぞれの政策が国民生活や日本経済全体にどのような影響を与え、物価高に対して真に有効な手段は何なのかという、より本質的な議論が求められています。有権者は提示された政策の表面的な部分だけでなく、その背景や効果、そして財源についても理解し、投票に臨む必要があります。