作家で日本維新の会参議院幹事長でもある猪瀬直樹氏は、新著『戦争シミュレーション』で日米戦争勃発の深層を探る。ジャーナリストの田原総一朗氏との対談で注目される彼の戦争観は、データ軽視と集団的想像力が戦争をいかに招いたかという核心的な問いを投げかける。本稿では、猪瀬氏の代表作からその考察を紐解く。
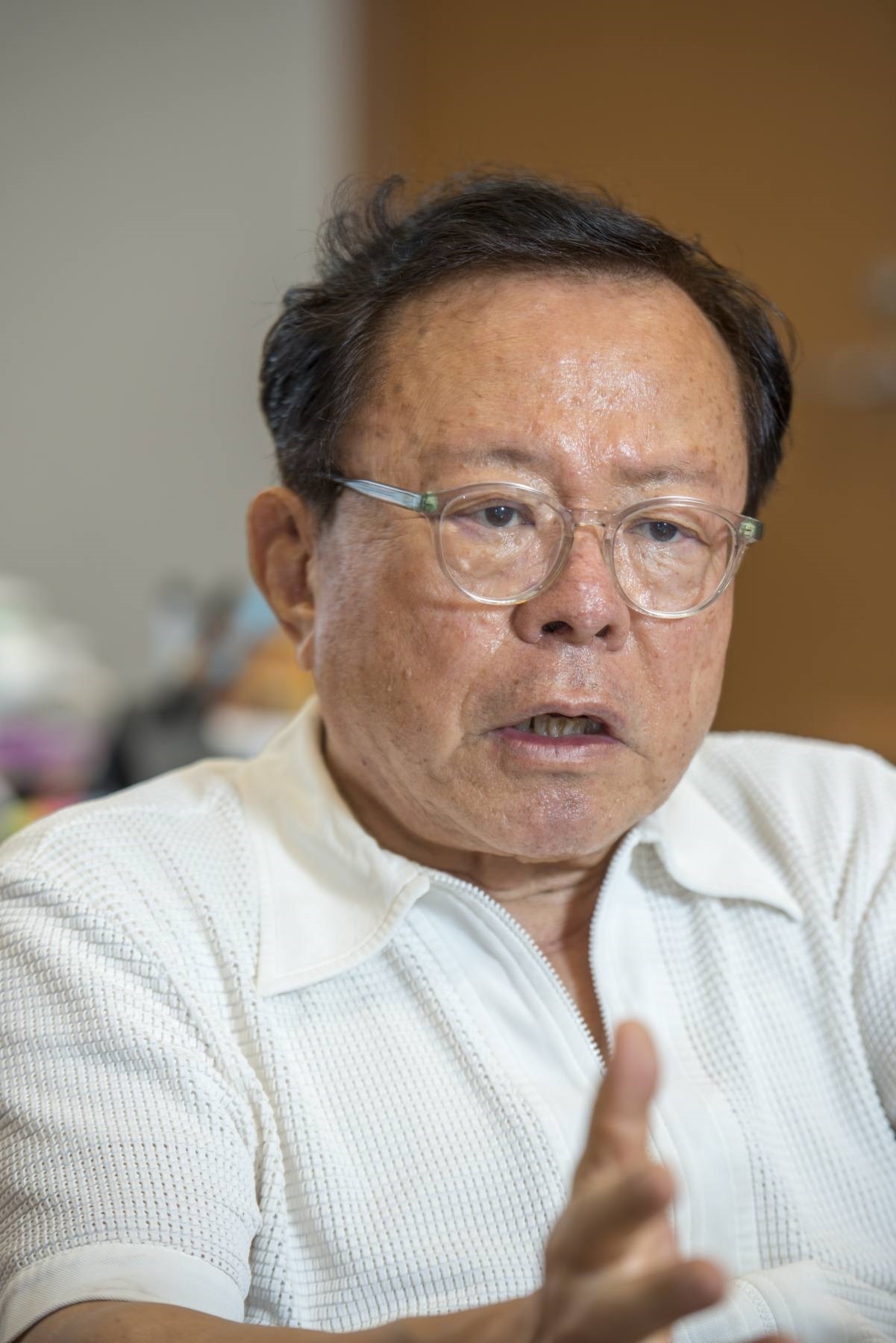 作家・政治家として知られる猪瀬直樹氏の肖像。日米戦争の深層を分析する彼の視点を示す。
作家・政治家として知られる猪瀬直樹氏の肖像。日米戦争の深層を分析する彼の視点を示す。
『昭和16年夏の敗戦』が示す「精神論」の危険性
なぜ日本は、勝利の見込みがないにもかかわらず日米戦争へと雪崩れ込んだのか。この近代日本を読み解く必須の問いに、猪瀬氏は1983年の著書『昭和16年夏の敗戦』で迫った。開戦前夜の1941年夏、官庁・陸海軍・民間の若手俊秀からなる総力戦研究所が行ったシミュレーションは明確に「日本必敗」と結論付けていた。戦争遂行に不可欠な石油の枯渇など具体的なデータが示されたにもかかわらず、当時の東條英機陸軍相(後の首相)らは、これを「机上の空論」と軽視。一国の運命を決める意思決定が、客観的なロジックではなく、前例踏襲やその場の「空気」、責任回避の論理で決せられていたという衝撃的な舞台裏を検証し、精神論がデータや現実を凌駕する危険性を浮き彫りにする。
『黒船の世紀』で紐解く「共同幻想」と開戦
猪瀬氏はさらに、「日本人の精神史」という別の角度から日米戦争の背景に肉薄した。それが1993年の作品『黒船の世紀』だ。この著作では、1904〜05年の日露戦争以降、日米双方で「日米未来戦記」というジャンルの読み物が大流行した点に着目。日本側には、ペリーの黒船来航で泰平の夢を破られ、弱肉強食の世界に投げ込まれたことによる潜在的な対米恐怖症、いわゆる「黒船トラウマ」が存在した。一方、米国側では、日露戦争での日本の勝利が「日本脅威論」を煽り、欧州に端を発した「イエロー・ペリル(黄禍論)」が伝播し、対日移民規制の動きとも連動していた。このように、戦争は単なる現実的要因だけでなく、太平洋を挟んだ両国間に形成された集団的な想像力、すなわち「共同幻想」によって呼び寄せられ、必然ならざる必然を生むというメディア史的側面が検証されている。
猪瀬直樹氏の二著作は、日米戦争への突入が、国力差や戦略的判断だけでなく、非合理な意思決定、そして両国間の集団的「想像力」や「恐怖」が複雑に絡み合って生まれたことを浮き彫りにする。現代の日米関係や、参政党現象に見られるような社会の動向を考察する上でも、彼の戦争観は示唆に富んでおり、過去から学ぶことの重要性を改めて問いかける。






