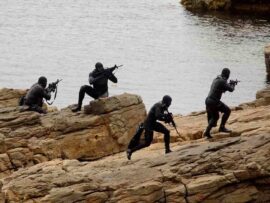鹿児島県・トカラ列島近海で、6月21日以降、震度1以上の地震が1600回を超える頻度で発生しています。特に、7月3日には十島村の悪石島で最大震度6弱、マグニチュード(M)5.5の地震が観測されました。これらの地震活動は、海底の活断層における横ずれ断層運動が一因とされています。
[ トカラ列島の位置図。今回の群発地震の発生海域を示す。]
トカラ列島の位置図。今回の群発地震の発生海域を示す。]
この海域では、2021年12月にもM6.1の地震が発生しており、今回と同様の群発地震が再び発生した形です。トカラ列島近海は、太平洋底を形成するフィリピン海プレートと、その上部に位置する奄美海台と呼ばれる海底の隆起部が、トカラ列島や沖縄本島を含むユーラシアプレートの下に沈み込んでいる、地殻変動が非常に活発な地域です。
琉球海溝と沖縄トラフ:活発な地殻変動の背景
ユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込む境界には、長さ約1000キロメートルに及ぶ巨大な谷「琉球海溝」が存在します。この琉球海溝は、M9クラスの海溝型巨大地震の震源域とも重なる可能性があります。また、トカラ列島の西側には、海底が拡大しつつある凹地「沖縄トラフ」があり、これらの地形はいずれも活発な地殻活動を示唆しています。
群発地震のメカニズム:プレートの応力と断層
現在のトカラ列島近海における群発地震は、プレートの沈み込みによって地殻に絶えずかかる応力(ひずみを生じさせる力)が蓄積され、陸側のユーラシアプレート上部がそれに耐えきれなくなって割れることで発生しています。これにより、横ずれ型の断層運動だけでなく、上盤側がずり下がる正断層型の直下型地震も頻繁に起きています。
マグマ活動の可能性
さらに、この海域には断層だけでなく古い火山の痕跡も確認されており、地下深部でマグマが上昇しつつある可能性も指摘されています。今回の群発地震の中には、深さ30キロメートルといった深い場所を震源とする地震もあり、活断層の活動だけでなく、マグマの動きが地震活動に関与している可能性も否定できない状況です。
南海トラフ巨大地震との関連は?
琉球海溝で発生する巨大地震が、西日本の太平洋沖で発生が予測されている「南海トラフ巨大地震」と連動するのではないかという懸念も一部にはあります。しかし、現在のところ、琉球海溝に関する観測データは非常に乏しく、現在の地震学では両者の連動について予測することは困難です。
なお、過去の地震記録や地殻変動データを分析した結果から、南海トラフ巨大地震は2030年代には高い確率で発生すると予測されています。この予測は、約1500年前に遡る古文書の地震記録などを基に行われていますが、トカラ列島を含む琉球海溝については、こうした古文書の記録がほとんど残されていません。そのため、この地域における巨大地震の発生を予測することは、南海トラフに比べてはるかに難しい状況です。
南海トラフ巨大地震の予測に関する詳細は、関連する専門的な分析を参照することが望ましいでしょう。
まとめ
トカラ列島近海で続く群発地震は、活発なプレート沈み込みや断層活動、そして潜在的なマグマ活動など、複雑な地下構造が引き起こしている可能性が高いと考えられます。琉球海溝における巨大地震と南海トラフ巨大地震の連動については、現時点では科学的に予測が難しく、さらなる観測と研究が求められています。この地域の地震活動については、引き続き注意深い監視が必要です。