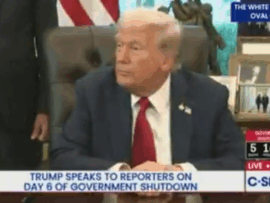東京大学における女子学生の比率はわずか2割。「東大は男子がデフォルト」とまで言われる環境で、自らの道を探求する女性たちの声を集めた新書『東大女子という生き方』(文春新書/秋山千佳・著)のコミカライズ版が電子書籍として配信開始されました。この話題作を手がけた東大卒マンガ家ハミ山クリニカ氏が、原作著者・秋山千佳氏との対談で、母娘関係、女性のキャリア形成、進路選択など、「東大女子」ならではのリアルな経験と葛藤を明かしています。
「東大女子」のリアルな葛藤:ハミ山クリニカ氏の視点
コミカライズ作品の主人公である初音とイズミのキャラクターには、作者自身の経験が色濃く反映されています。ハミ山氏は、ロールモデルが身近にいない中で試行錯誤しながら進む初音の姿に、大学時代の自分を重ね合わせました。一方、何でも相談し合える友人イズミのような存在がいれば、と当時を振り返ります。この経験は、脳科学者の中野信子氏が語る「友達が財産」という言葉の重みを再認識させるものでした。東大女子を取り巻く環境は特殊であり、その中で築かれる友情の価値は計り知れないものがあります。
東大入学の意義と「進学選択」の現実
漫画では、初音が友人イズミとの交流を通して、「やりたいことが決まっていないからこそ東大に来てよかった」という独自の結論に至る姿が描かれています。ハミ山氏も、受験時点で明確な目標を持つ学生は少ないとし、入学後に学部学科を選べる東大のシステムは大きな利点だと語ります。しかし、その裏には2年生途中までの成績で希望学科が決まる「進学選択」という厳しい現実が存在します。まるで再度の受験に挑むようなプレッシャーの中で勉強に励む日々は、多くの東大生が経験する共通の苦労です。ハミ山氏自身も、この制度と厳しい卒業要件のために、大学4年間で学業以外の余裕がほとんどなかったという後悔を抱いています。
 東大卒マンガ家ハミ山クリニカ氏の作品より、東大女子の成長と葛藤を描く場面。
東大卒マンガ家ハミ山クリニカ氏の作品より、東大女子の成長と葛藤を描く場面。
「東大女子あるある」が示す社会の期待と内面の葛藤
世間一般が抱く「東大女子」へのイメージと、彼女たち自身の現実にはギャップがあります。ハミ山氏が自身の研究室の人々を家族のように慕い、大学が居場所になっていた経験は、学問の楽しさと苦しさの両方を物語ります。しかし、卒業後、特に子どもを持つようになってから、「お子さんも東大だね」と周囲から言われることが増え、戸惑いを感じるといいます。これは「東大女子あるある」の典型であり、自身が経験した勉強の厳しさを知っているからこそ、子どもに同じ道を無理強いしたくないという親心も覗かせます。子どもにはプレッシャーを感じることなく、自由に生きてほしいという願いは、東大女子が社会から受ける無言の期待と、彼女たちの内なる葛藤を浮き彫りにしています。
結論
『東大女子という生き方』のコミカライズは、単なる学歴物語ではなく、個人の成長、友情の力、そして社会の期待と自身のアイデンティティの間で揺れ動く女性たちの複雑な心情を描き出しています。東大という特殊な環境下で、学び、悩み、そして自己を確立していく「東大女子」たちのリアルな声は、多くの読者にとって共感を呼び、多様な生き方について深く考えるきっかけとなるでしょう。