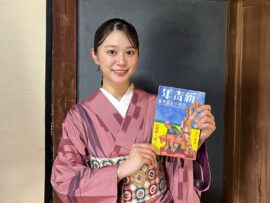日暮里駅は、JR東日本の京浜東北線、山手線、常磐線、京成電鉄、そして日暮里・舎人ライナーが乗り入れる、東京の重要な交通拠点の一つです。2023年度のJR東日本・日暮里駅の1日平均乗降人員は10万2143人、京成電鉄は2024年度に10万1435人、日暮里・舎人ライナーも2023年度に5万2085人を記録し、毎日多くの人々がこの駅を利用しています。特に、成田空港と都心を結ぶ京成スカイライナーの全列車が停車し、日暮里・舎人ライナーからのJR線への乗り換え客も多い、極めて重要な結節点です。
これほどまでに多くの路線が交差し、利用者が多いにもかかわらず、日暮里駅に対して「地味」「ぱっとしない」といった印象を抱く方も少なくありません。大規模な駅ビルや商業施設の整備が他主要駅に比べて進んでいないのはなぜでしょうか。本稿では、日暮里駅が持つ独特の特性と、その発展を阻む意外な理由について深く掘り下げていきます。
 日暮里駅の全景と複雑な地形、多数の路線が乗り入れるターミナル駅の様子
日暮里駅の全景と複雑な地形、多数の路線が乗り入れるターミナル駅の様子
利用者数に見合わない駅ナカ施設の現状
日暮里駅は、山手線や京浜東北線で上野駅の次に位置し、常磐線の起点でもあります。JR東日本の駅構内には、駅ナカ施設「エキュート日暮里」が設置されていますが、その規模は決して大規模とは言えません。店舗数は28店に限定され、座って食事を楽しめるイートインやカフェはそれぞれ1店舗のみとなっています。その他の店舗も、弁当や総菜、お菓子といったテイクアウト中心の小規模な構成で、駅構内の一部を占めるに過ぎません。
対照的に、日暮里駅よりも都心部に位置する上野駅では、広大な敷地を活かした大規模な駅ナカ商業施設が充実しており、利用者の利便性や満足度において日暮里駅とは大きな隔たりがあります。日暮里駅のように、複数路線の乗り換え客が集中する主要な交通結節点であれば、もっと駅ナカ施設が充実していても不思議ではないと感じる利用者は多いはずです。この現状は、日暮里駅の「ぱっとしない」印象をさらに強くする要因となっています。
日暮里駅の発展を阻む「高低差」と「地形的制約」
では、なぜ日暮里駅は、その高い交通需要に見合った施設整備や大規模な再開発が進まないのでしょうか。その最大の理由は、駅周辺の極めて複雑で特徴的な地形にあります。
西側の急斜面と広がる谷中霊園
日暮里駅の西側には、まるで崖のような急峻な斜面が広がっており、その高台の上には広大な谷中霊園や歴史ある天王寺が位置しています。駅自体が、この高台の縁に沿うように設けられており、地形的に非常に厳しい条件下に立地しています。谷中霊園と駅のホームとの間には明確な高低差があり、この自然の障壁が西側への駅機能の拡張を困難にしています。
 日暮里駅の西側に広がる急な斜面と線路、高低差が顕著な駅周辺の地形
日暮里駅の西側に広がる急な斜面と線路、高低差が顕著な駅周辺の地形
東側の低地と複雑な道路構造
一方、駅の東側は西側とは対照的に低地が広がっています。京成電鉄の日暮里駅は、JRの駅の東側に位置しており、その地盤はJRのホームよりも一段低い構造です。この東西の高低差により、日暮里駅は水平方向にも垂直方向にも、大規模な拡張や再開発を行うための余地がほとんどありません。既存の地形が、新たな施設建設や都市開発の大きな障壁となっているのです。
駅周辺の道路構造もまた、こうした地形的制約を色濃く反映しています。JR日暮里駅の西口を出た道路は、線路をまたぐ形で北口へと向かい、そこから京成日暮里駅に沿って急な坂道を下ります。その坂道の先にようやくロータリーがあるという、非常に複雑な動線となっています。このような複雑な道路ネットワークは、駅周辺の土地利用の効率性を低下させ、開発をさらに難しくしています。
日暮里・舎人ライナー駅も地形の影響下
日暮里・舎人ライナーの駅も、この地形の影響を強く受けています。JR駅や京成駅とは接続しているものの、東側のロータリーのすぐ上、地上からかなり高い位置に設置されています。この想像以上の高低差は、利用者のアクセスに大きな問題を引き起こすわけではありませんが、やはり駅周辺に多様な商業施設や公共施設を配置できるほどの空間的余裕をほとんど与えていません。
結論
日暮里駅が「ぱっとしない」という印象を持たれ、大規模な発展が遅れている主な理由は、その利用者数の多さや交通結節点としての重要性にもかかわらず、駅周辺の極めて厳しい地形的制約にありました。駅の西側に広がる急峻な斜面、東側の低地、そして複雑な高低差を持つ地盤が、水平方向にも垂直方向にも拡張の余地をほとんど奪い、大規模な開発や再整備を困難にしています。
このような物理的な制約が、駅ナカ施設の規模や駅周辺の商業集積にも影響を与え、日暮里駅が他の主要ターミナル駅と比べて「地味」に映る要因となっています。しかし、この「地味さ」は、歴史的な谷中・根津・千駄木エリア(通称「谷根千」)の風情を保ち、都会の喧騒から一歩離れた独特の雰囲気を醸し出す一因とも言えるでしょう。日暮里駅の将来的な発展を考える上で、これらの地形的制約をいかに克服し、あるいは共存していくかが、今後の都市開発における重要な課題となるでしょう。