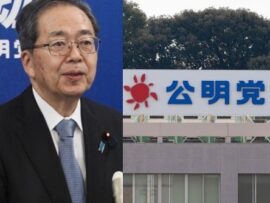現代の無人販売所は、監視カメラ、ロッカー、QRコード決済といった最新の防犯・決済システムを導入し、セキュリティ対策に注力しています。しかし、その一方で、あえて盗難防止策を講じない選択をする地域も存在します。この対照的な運営の背景には、数値では測れない「面識経済」という概念に基づいた、地域コミュニティにおける深い信頼と人間関係があるのです。本稿では、山崎 亮氏の著書『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(光文社)からの抜粋を基に、日本の無人販売所が辿ってきた歴史と、それに伴う地域社会の変化を深掘りします。
 新鮮な野菜が並ぶ無人販売所のイメージ。現代的な防犯対策や決済システムを連想させる外観。
新鮮な野菜が並ぶ無人販売所のイメージ。現代的な防犯対策や決済システムを連想させる外観。
「もったいない」から始まった無人販売所の原点
各地を巡る中で、共同売店と並んで筆者が特に興味を持つのが「野菜の無人販売所」です。その誕生と歴史的変遷は、畑で野菜を育てる農家の日常から自然発生的に始まったと想像されます。農家が丹精込めて収穫した野菜の中には、形が曲がっていたり、傷がついていたりして、出荷基準を満たさないものがあります。また、市場の需要を超える量を収穫してしまう日もあります。こうした「規格外」や「過剰」な野菜は、自宅で消費しきれないことが少なくありません。
最初は、余った野菜を近所の親戚や友人に「おすそ分け」するという、顔が見える関係性の中での共有が行われていました。これは、日本の地域社会に深く根差した相互扶助の精神であり、「面識的なやりとり」の典型です。しかし、多くの住民が農家である地域では、同じ時期に同じ野菜が豊富に収穫されるため、受け取り手が限られるという課題が生じます。せっかく育てた野菜を捨てるのは「もったいない」という思いから、「誰か欲しい人はいないだろうか」という発想が生まれます。こうして、畑の脇に簡素な棚を設け、そこに余剰野菜を並べて「ご自由にお持ちください」と置く「無料配布所」が誕生したのかもしれません。
道の通行人が棚を見つけ、必要な野菜があれば喜んで持ち帰ります。畑の持ち主が近くにいれば一声かけ、姿が見えなければ感謝のメモを残したり、代わりに何かを置いたりする。集落で見かけた際には改めてお礼を伝えるなど、まさに地域住民間の信頼と直接的な人間関係、すなわち面識関係が基盤となったやり取りが行われていました。誰がどこの畑の持ち主かを知っているからこそ、こうした感謝や交流が生まれるのです。
信頼が形を変える:お金が介在する販売所へ
しかし、この無料配布の形態にも変化が訪れます。ある利用者から「お金を取ってくれた方が、気兼ねなく野菜を持ち帰れるから気が楽だ」という声が上がったのかもしれません。感謝の品を考えたり、メモを書いたりする手間を省きたいという気持ちも、ごく自然なことです。このような利用者のニーズに後押しされ、畑の持ち主は棚の脇にザルや箱を置き、「野菜、すべて100円」といった張り紙をするようになりました。ここに「無人販売所」という、現代に通じる形態が確立したと考えられます。
金銭が介在するようになったことで、人々は小銭をザルや箱に入れますが、そこには購入者の名前が書かれることはありません。畑の主人は、誰がどの野菜を買ってくれたのかを直接的に知ることができなくなります。以前は「いつも美味しい野菜をありがとうね」といった直接の声掛けで初めて購入者を認識する、といった状況も生まれたでしょう。これにより、購入者と販売者の間にあった「面識関係」は、ある程度の匿名性を帯びるようになります。商品は依然として地域の生産者から直接供給される新鮮な野菜であり、地域社会の基盤となる信頼関係は残ってはいるものの、金銭のやり取りによって、以前のような密接で個人的な交流は希薄になっていったのです。
まとめ:無人販売所の進化が示すコミュニティの価値
無人販売所の歴史は、「もったいない」という日本人特有の精神から始まり、地域住民間の「おすそ分け」という面識経済の中で育まれました。それが利用者の利便性を追求する中で、金銭が介在する「販売所」へと形を変え、関係性の一部が匿名化されていく過程を辿ったことは興味深い事実です。
現代において、監視カメラやQRコード決済を導入する無人販売所が増える中、あえて防犯対策をしない場所が存在することは、数値や効率だけでは測れない、目に見えない「信頼」というコミュニティの財産がどれほど重要であるかを私たちに問いかけています。無人販売所は単なる販売の場に留まらず、地域における人間関係の変遷、そして信頼という無形の価値を映し出す鏡なのです。
参考文献
山崎 亮『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(光文社)