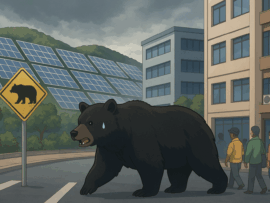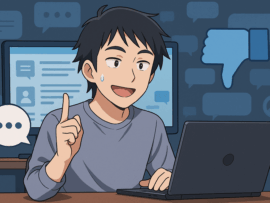東日本が梅雨明けを迎え、日本列島が本格的な酷暑に突入する中、フランス・パリに暮らす女優の杏さんが自身のYouTubeチャンネルで配信した「パリの記録的な猛暑。クーラーがありません…[報告&対策]」が大きな話題を呼んでいます。北海道よりも高緯度に位置するパリでさえ40℃近い猛暑が続くにもかかわらず、現地の条例によりエアコンの設置が極めて困難であるというのです。なぜこのような状況が生まれるのか、そしてその対策はあるのでしょうか。パリ在住のジャーナリスト、広岡裕児氏による詳細な現地レポートと、背景にあるフランスの法規制を掘り下げていきます。
杏が直面したパリの「クーラーがない」現実
 パリの猛暑とクーラーのない生活についてYouTubeで語る女優・杏
パリの猛暑とクーラーのない生活についてYouTubeで語る女優・杏
女優の杏さんが今月初めにパリを襲った災害級の猛暑についてYouTubeで報告した内容は、多くの日本人にとって驚きでした。動画の中で杏さんは、パリには元々クーラーがほとんど普及していないことを説明し、「異常気象になっても条例としてクーラーがつけられない。パリの美しい街並みの景観を守るために室外機を外に出してはいけない」と語っています。さらに、「もし設置するとしても、建物に住む全員の承諾や様々な許可が必要で、やっとつけられる」とその困難さを明かしました。杏さんの言葉通り、パリではクーラーの室外機を無許可で外部に設置することはできません。これはエアコンに限らず、パリの景観を守るための広範な規制の一環なのです。
フランスにおける「個人と社会」の明確な区別
フランス社会では、個人の自由と社会の調和という概念が明確に区別されています。個人は、他者の自由を侵害しない限り、何を考え、何をしても自由です。しかし、他者と関わる「社会」においては、共存のために厳格なルールが必要とされます。マンションなどの共同住宅に例えると、窓枠の内側は個人の「専有区画」であり、居住者は自由に装飾したり、壁の色を変えたりできます。しかし、窓の外側、つまり建物の「外観」は社会的な共有部分と見なされ、その変更には細かい規制が適用されるのです。この原則は、パリの歴史的建造物や街並みの保護に大きく寄与しています。
室外機設置を阻む「外観変更」と複雑な申請プロセス
クーラーの室外機設置が困難な主要な理由の一つは、フランスの都市計画法典に基づく「外観変更工事」に関する規定です。建物の外観を変更する工事を行う場合、コミューン(市町村に相当する行政区画)への事前申請が義務付けられています。例えば、広々としたバルコニーがあり、室外機が外部から完全に隠れるような構造であれば問題ないかもしれませんが、通常、室外機を設置すると外観変更に該当してしまいます。
コミューンやその連合体は、地域都市計画プラン(PLU)という包括的な計画に基づき、土地の用途、建築基準、景観などを総合的に審査します。住民からの申請はこれに照らし合わせて審査され、約1ヶ月以内に返答がなされるのが一般的です。さらに、文化遺産保護の対象となっている建物や、その周囲500メートル以内にある建物の場合、文化省所属のABF(フランス建造物建築家)の同意も別途必要となります。これらの規制はパリ市街に限定されるものではなく、郊外の一戸建てであっても工事申請が必要な場合があり、地域によっては室外機をむき出しで置くことが許されず、木製の枠で囲うなどの配慮が求められることもあります。
共同住宅における「管理組合」の壁
共同住宅でのエアコン設置には、さらに管理組合(共有組合)の承諾という大きな壁があります。設置を希望する居住者は、要請書と詳細な設置計画書を管理会社に書留郵便で送付し、次の管理組合総会で住民全員の承諾を得る必要があります。しかし、クーラーの室外機は、特にパリの歴史ある建物においては、その異質な外観から不動産の価値を損なうと見なされることが多く、住民からの反対に遭う可能性が非常に高いのが現状です。これは、個人の快適さよりも、共有財産としての建物の統一性や価値を重視するフランス社会の特性が強く反映されています。
パリが記録的な猛暑に見舞われる中、エアコンの普及を阻むのは、単なる設備の問題ではなく、美しい景観を守るための厳格な法規制、個人の自由と社会の調和を重んじる文化、そして共同住宅における複雑な合意形成プロセスという多層的な要因が絡み合っていることが分かります。女優・杏さんの体験談は、異文化における生活の難しさや、気候変動がもたらす新たな課題を浮き彫りにしています。
参考文献
- Original article by dailyshincho.jp via Yahoo! News: https://news.yahoo.co.jp/articles/f39fd0defae545aaf6f6d3e0efe20b37b292ed02