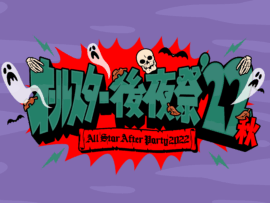7月20日に行われた参議院議員選挙では、与党が過半数の議席を下回る結果となり、歴史的な敗北を喫しました。その一方で、「日本人ファースト」を掲げる参政党が選挙区で7議席、比例代表で7議席を獲得し、合計14議席と大きく躍進しました。外国人政策をはじめ、多岐にわたる議論が交わされた今回の選挙を、エジプト出身のタレント・フィフィ氏がどのように分析したのか、その視点に注目します。
若年層の「危機感」と投票行動の変化
今回の参院選における年代別比例投票の出口調査からは、明確な傾向が読み取れます。高齢者層が自民党や立憲民主党などの既存政党を支持する割合が高い一方で、若年層では参政党や国民民主党といった新興政党への支持が顕著に増加しているのです。これは、現状の日本や日本を取り巻く国際情勢に対して強い危機感を抱き、「現状を変えたい」と願う層が若者に多いことを示唆しています。テレビのワイドショーが「誰かの健康状態」や「海外の皇室事情」といった“平和”なニュースを報じる中、世界的に見れば日本は物価高の中でも比較的経済が安定しているため、これまでは「この国を変えなければ」という意識が芽生えにくかったかもしれません。しかし、現在のSNS社会では国際情勢のニュースが絶え間なく流れ、桁違いの情報量に触れる若者たちは、「明日の日本は本当に平和を保てるのか?」「将来、ちゃんと生活できるのか?」といった懸念を抱いているのでしょう。参政党が議席を14まで伸ばしたのは、既存政党が十分に拾いきれなかった層を巧みに取り込んだ結果と言えます。
メディアの「本音」と選挙制度への問いかけ
今回の選挙は、選挙制度やマスメディアのあり方についても深く考えさせられる機会となりました。特に注目されたのは、7月21日の情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日系)での元テレビ朝日局員、玉川徹氏(62)の発言です。玉川氏は、「ここ10年、どんどん選挙に行かなくなった人が(今回の参院選に)行った。そういう人、誰が行ったかを分析しないといけない」「今まで選挙に興味がない、政治に興味のない人がたまたまSNSやショート動画を見て、そこで触れてっていう話」「(これまでは)基本知識を持っている人が選挙に行っていた」と述べ、これが物議を醸しました。フィフィ氏は、この発言にマスメディアの“本音”が凝縮されていると感じたと言います。彼女には、これが「SNSで情報を得ている人たち」が投票すること自体に疑問を呈しているように聞こえたとのことです。
 ニュース番組で発言が注目される玉川徹氏。2025年参院選に関する彼のコメントは物議を醸した。
ニュース番組で発言が注目される玉川徹氏。2025年参院選に関する彼のコメントは物議を醸した。
今回の参院選では投票率が上昇し、15年ぶりに50%後半を記録しましたが、それでもまだ低い水準です。より多くの有権者が選挙に参加すべきであり、メディアには有権者を失望させない報道が求められます。例えば、東京選挙区から無所属で出馬した平野雨龍氏(31)は、連日の熱心な街頭演説がネット上で大きな話題を呼び、主要駅前には多くの聴衆が集まりました。実際に23万票を獲得したものの、惜しくも落選。無所属候補はテレビで取り上げられる機会が少ないにもかかわらず、健闘したと言えます。一方で、約10万票の得票数で当選している候補者も存在します。これは選挙制度の問題でもありますが、「結局、投票に行っても自分たちの声は届かない」と若者に思わせてしまうと、さらなる選挙離れが進む懸念があります。小さな政党や無所属候補がメディアに取り上げられにくい現状は、公平性に欠けるとの指摘も上がっています。
政治家への「圧力」と有権者の期待
今回の参院選の結果は、与党も野党も、そして大きく議席を伸ばした参政党も含め、各政党に大きなプレッシャーを与えていることでしょう。有権者の関心事が以前にも増して敏感に把握され、戦後目を背けてきたものの、今こそ議論を進めなければならない課題がいくつも浮上してきました。各政党は、選挙前に掲げた公約を必ず実行することが求められます。口にしたからには行動に移さなければ、有権者の期待を裏切ることになるからです。
参考文献:
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/01b2e5f6ddfd106fa8348278813c7a65a89e8c37
- NEWSポストセブン (オリジナル記事の掲載元): https://www.news-postseven.com/
- テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」: https://www.tv-asahi.co.jp/m-show/