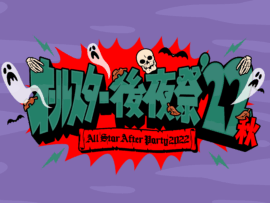近年、大学を選ぶ上で「就職の強さ」が重要な評価軸となっています。多くの読者に25年以上選ばれ続けてきた大学案内『大学図鑑!』は、現役生やOB・OG、5000人を超える「ナマの声」をもとに、各大学の就職事情を詳細に分析しています。本記事では、その最新版『大学図鑑!2026』(2025年1月時点の執筆情報に基づく)から、特に注目される日東駒専グループの中から、日本大学のリアルな就職事情に焦点を当て、その実態と学生の本音をお届けします。
 就職活動に臨む大学生のイメージ
就職活動に臨む大学生のイメージ
日本大学における就職への関心と実態
日本大学の学生(日大生)は就職への関心が非常に高い傾向にあります。しかし、その関心は必ずしも仕事内容そのものへの深い探求ではなく、「どうすれば世間的に聞こえの良い会社、あるいは将来的に得になりそうな会社に入れるか」という方向に向けられがちです。このような日大生にとって、心の支えとなっているのは「OBの多さ」です。同じくらいの偏差値帯の大学と比較して、「OBが多い分、就職に有利に違いない」という期待感が根強くあります。
ある商学部のOBは、「就職に関しては、日東駒専グループというより、明治や中央あたりに近い感覚じゃないかな。少なくとも法政には勝っていると思う」と語っています。就職は個人の問題であるにもかかわらず、このように語りたがるところが、非常に日大らしい、あるいは“そこそこの私立大学”全般に共通する心理と言えるでしょう。
就職支援の実効性と学生の認識
日本大学では、テレビ局、新聞社、出版社を目指す学生向けのマスコミガイダンスなども開催されています。しかし、学生たちの間には、大学の就職支援に対する冷静な視点も存在します。文理学部の学生からは、「就職課は就活に強い大学だと豪語しているけれど、実際はそうでもない」といった、やや冷めた意見も聞かれます。
実際の就職戦線での実感としては、経済学部のOBが語るように「中小企業なら楽勝、中堅企業は少し厳しい、大手企業はとっても厳しい」というのが多くの学生の実感です。法学部のOBからは、「一流どころに大学名でギリギリ落とされないラインかどうかは、その年の採用情勢に大きく左右される」という声も上がっています。確かに、学生数の母数が非常に大きいこともあり、驚くような一流企業から内定を得る学生も少なからず存在します。
リアルな情報に基づく就職活動の重要性
日本大学の就職事情は、学生自身の意識、OBネットワークへの期待、そして大学の支援と現実とのギャップなど、多面的な要素が絡み合っています。就職活動は最終的に一人ひとりの努力と能力に委ねられる部分が大きいですが、今回ご紹介したような『大学図鑑!』に集約されたリアルな声は、今後の進路選択や就職戦略を考える上で貴重な情報となるでしょう。学生は、単なる表面的な情報に惑わされず、多角的な視点から現実を把握し、自身のキャリアプランを築くことが求められます。
本記事は『大学図鑑!2026』(2025年1月時点の執筆情報に基づく)より一部抜粋、再編集したものです。