かつて2010年代後半、日本で巻き起こった「高級食パンブーム」を覚えている読者も多いだろう。1本2斤で1000円弱という高価格帯の食パンは、「暮らしのプチ贅沢」や「手軽なギフト」として瞬く間に浸透し、一説には最盛期には1000店舗以上の専門店が林立したと言われる。しかし、その盛り上がりは一過性のトレンドに収束し、多くのブランドが大量閉店の憂き目に遭った。飲食業界における栄枯盛衰は常だが、なぜこれほどまでに熱狂的なブームが生まれ、そしてなぜ終焉を迎えたのか。本稿では、ブームの立役者の一つである「銀座に志かわ」の事例を通して、その背景と構造を深掘りする。
ブームを牽引した「生食パン」の魅力と売上実績
新型コロナウイルス感染症が拡大する直前、筆者の近所にも高級食パン専門店があり、連日行列ができていた光景が記憶に残っている。開店時間の午前10時を待ち、休日には30〜40人が焼きたてのパンを求める様子を傍目に見ながら、市販の3〜4倍近い価格にもかかわらず、なぜこれほど飛ぶように売れるのか疑問に感じていた。中には白無地の化粧箱に入った食パンを両手に抱える客も見受けられ、数千円分の食パンを購入する光景は異様にも映った。
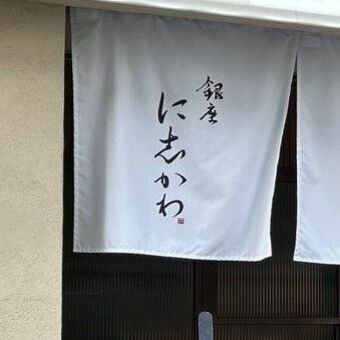 高級食パンブーム時の銀座に志かわ店舗にできる行列と人気の食パン
高級食パンブーム時の銀座に志かわ店舗にできる行列と人気の食パン
ブームの一翼を担った「銀座に志かわ」の親会社、OSGコーポレーション代表取締役の湯川剛氏は、全盛期を振り返り、「1店舗で仕込める食パンは1日で最大約600本。それが連日、全国の多くの店舗で完売していた。ブランドを立ち上げた2018年から2021年頃までは売上も店舗数も右肩上がりで、高級食パンが当たり前に定着したものだと錯覚するほどだった」と語る。当時、「銀座に志かわ」の食パンは税込864円で販売されており、1日600本が完売すれば、単純計算で日計50万円を超える売上となる。
なぜ人々はこれほどまでに高級食パンの虜になったのか。これまで「暮らしの中のプチ贅沢」や「気の利いた手土産」がヒット要因として語られてきたが、湯川氏の話からはブームの別の側面が見えてくる。そして、この流行に乗じて急速に店舗展開を進めた他社ブランドが軒並み大量閉店に追い込まれた背景も明らかになった。
異業種参入が招いたブームの終焉とブランドの淘汰
高級食パンブームの火付け役は、2013年に大阪で創業した「乃が美」とされる。卵を使わずに生クリームや蜂蜜でしっとり甘く仕上げた生地は、そのまま食べても美味しい「生食パン」として話題を集めた。それまで食パンといえばトーストして食べるのが一般的だったため、テレビで「とろける食感」「ふわふわの生食パン」と紹介されると、その物珍しさも相まって実店舗には長蛇の列ができた。
このブームは、一見するとシンプルなビジネスモデルに見えたことから、多種多様な異業種からの参入を促した。高い利益率が見込まれ、専門的なパン製造の経験がなくても比較的容易に始められるという認識が広がった結果、市場は急速に飽和状態に陥った。新規参入が相次ぐ中で、消費者の目新しさが薄れると、価格競争や品質の差別化が難しくなり、供給過多に陥った市場から多くのブランドが淘汰されていったのである。
ブーム終焉から見えてくる日本市場の教訓
高級食パンブームの栄枯盛衰は、日本の消費トレンドと飲食ビジネスにおける重要な教訓を示している。一時的なブームは、消費者の新たなニーズや「プチ贅沢」といった心理を巧みに捉えることで急速に拡大する一方で、ビジネスモデルの模倣の容易さや、長期的なブランド戦略の欠如が、市場の飽和と急速な衰退を招くことを浮き彫りにした。
しかし、「銀座に志かわ」のように、苦境を経て事業の方向転換を図り、生き残りを図るブランドも存在する。彼らの事例は、単なる一過性の流行に終わらず、変化する市場環境に適応し、独自の価値を提供し続けることの重要性を物語っている。高級食パンブームの終焉は、日本における飲食ビジネスの厳しさと、持続可能な成長のための経営戦略の重要性を再認識させる出来事であったと言えるだろう。






