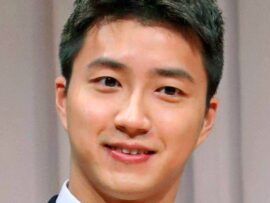日米両政府間で合意された貿易交渉により、米国が日本からの自動車輸入に課す追加関税が25%から15%に引き下げられる見通しとなりました。これには、見返りとして米国車に関する日本の規制緩和も盛り込まれています。この合意が、米国車の日本市場への影響、そして日本から米国へ自動車を輸出するメーカー、さらには関連部品メーカーにどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきます。
米国車輸入への「追い風」:規制緩和の期待
今回の合意の「見返り」の一つが、米国車の日本市場における規制緩和です。輸入車専門の販売店「キャルウイング」の植野史祐竜氏によれば、同社の在庫約70台のうち約8割がダッジ、キャデラック、ジープといった「アメ車」です。トランプ前大統領が求めていた「アメリカ車の市場開放」は、現在、日本が歩行者衝突試験などの国際基準を採用しているのに対し、米国独自の基準にはその義務がないため、米国車は改めて衝突試験を受ける必要がありました。
加えて、ウインカーの色変更、シートベルト警告灯の設置、騒音や排ガス試験など、日本市場向けに多岐にわたる改善が求められ、植野氏は「試験だけで300万円以上かかる車も存在する」と語っていました。しかし、今回の合意により、赤沢亮正経済再生担当大臣は「安全な米国メーカー製の乗用車を追加試験なく受け入れることで合意した」と発表。これを受けて植野氏は、「試験がなくなれば、その分安価で車を提供できる。アメ車業界にとって大きな追い風になる」と期待感を示しています。
 日本市場向けに改善が必要とされる米国車のウインカー
日本市場向けに改善が必要とされる米国車のウインカー
日本からの自動車輸出に立ちはだかる「25%関税」の影響
一方で、日本から米国へ輸出される自動車に対しては、今年4月から25%の追加関税が課されており、その影響はすでに日本の自動車メーカーの業績に現れ始めています。三菱自動車の松岡健太郎副社長は、「関税影響は144億円になった。どうやってカバーしていくかを考えなければならない」と厳しい状況を説明しました。同社は今年4月から6月の純利益が前年同期の294億円から97.5%減少し、約7億円に落ち込んだと発表しています。
愛知県岡崎市にある三菱自動車の工場は、海外への輸出拠点として機能しています。この工場で働く従業員からは「この先が心配」「どうやって立て直していくのか」「また(関税が)25%に戻る可能性もある。怖い」といった不安の声が聞かれました。今回の関税引き下げは一部の懸念を和らげるものですが、依然として日本の自動車産業全体が厳しい状況に置かれていることがうかがえます。今後、他の自動車メーカーの決算でも、同様の厳しい数字が示される可能性があります。
 愛知県岡崎市にある三菱自動車の工場外観
愛知県岡崎市にある三菱自動車の工場外観
部品メーカーの「本音」:15%でも依然厳しい現実
自動車産業を支える部品メーカーも、トランプ関税の影響を色濃く受けています。従業員数250人のメッキ加工会社「白金鍍金工業」では、売上の85%を自動車関連部品が占めています。同社の笹野真矢社長は、「トランプ関税の話があってから、顧客からメッキの価格を下げてほしいという話があり、厳しい状況だ」と語ります。現在、同社は価格を安くするための企業努力を進めているとのことです。
日米合意により自動車関税は15%に引き下げられる見通しですが、笹野社長は依然として厳しい状況が続くと見ています。彼は「生産メーカーを選ぶのは顧客の自由なので、一度決まった値下げ価格は守らなければならない」とした上で、「関税が25%から15%になったのは条件としてかなり良くなったが、もともとの2.5%という関税と比較すると、依然としてかなり高い関税であることに変わりはないので、なかなか厳しい状況だ」と本音を漏らしました。これは、最終的な価格競争力を維持するため、サプライチェーン全体でのコスト削減圧力が続くことを示唆しています。
 自動車のフロントグリルにメッキ加工を施す白金鍍金工業の工場
自動車のフロントグリルにメッキ加工を施す白金鍍金工業の工場
今回の米国の自動車関税引き下げは、日本市場における米国車輸入の障壁を緩和し、消費者にとっては多様な選択肢と価格メリットをもたらす可能性があります。しかし、日本から米国への自動車輸出に課される関税は依然として高く、日本の自動車メーカーやそのサプライチェーンにとっては、収益圧迫や先行き不透明感が払拭されたわけではありません。この貿易合意は、日米間の経済関係における複雑な「光と影」を浮き彫りにしており、日本経済、特に自動車産業は引き続き適応と戦略的な対応を求められるでしょう。
参考資料
- 2023年7月27日『有働Times』より、テレビ朝日