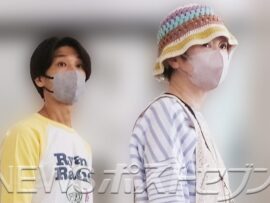参議院選挙で国民民主党からの公認取り消しを受けながらも、無所属での出馬という異例の選択をした山尾志桜里氏が、選挙戦後の心境と、公認問題の真相を「デイリー新潮」のインタビューで明かしました。なぜ、周囲からは「無謀」とも見えた挑戦にあえて挑んだのか。そして、自身を巡る一連の経緯の中、国民民主党や玉木雄一郎代表に対し、今、どのような思いを抱いているのでしょうか。この複雑な政治ドラマの舞台裏に迫ります。
 山尾志桜里氏、国民民主党からの公認取り消しを経て参院選に挑んだ後の表情
山尾志桜里氏、国民民主党からの公認取り消しを経て参院選に挑んだ後の表情
「中道政治」からの乖離、感じ始めた国民民主党の変化
落選から4日後の7月24日、インタビューに臨んだ山尾氏の声はかすれており、肌には日焼けの跡がくっきりと残っていました。参議院選挙東京選挙区での結果は、32人中16位での落選。心身ともに疲労の色が見え隠れするものの、その表情は晴れやかだったといいます。山尾氏がまず語ったのは、国民民主党からの公認取り消しに至るまでの経緯です。
「玉木代表からお誘いを受けた時点で、国民民主党が2020年の結党時とは異なり、少しずつ右傾化し、ポピュリズムに傾倒しているという違和感を覚えていました」と山尾氏は打ち明けます。党に戻るのであれば、結党時の「中道政治」の理念へ引き戻す役割を担いたいという強い思いがあったそうです。幹部からも憲法だけでなく、そうした役割を期待されているとの話もありました。しかし、「決まったようで決まらない」宙ぶらりんな扱いを受ける中で、「時すでに遅し、だったのかもしれない」と感じ始めていたと、当時の複雑な心境を振り返りました。
度重なる「待て」指示と公認発表の遅延
山尾氏が記者会見を望んでも、度重なる「待て」の指示で実現しなかったことには、党の対応への疑問がありました。4月22日、山尾氏の擁立が報じられた直後、SNS上での過去に対する批判を受けて、翌23日に予定されていた玉木代表、榛葉幹事長との出馬会見は急遽キャンセルに。その後も公認発表自体が延期され続けたといいます。
「まず『SNSの批判が落ち着くのを待とう』と1週間、次に『愛知に入らないでほしい』という突然の要望でさらに1週間、そして最後は『他の3人の候補者(足立康史氏、須藤元気氏、薬師寺道代氏)と一緒に公表したい』という理由で、もう1週間延期されてしまいました」。山尾氏は、一部の批判に浮き足立ったかのような党の対応に、ポピュリズムへの傾倒を感じざるを得なかったと説明します。結局、5月17日にようやく公認が発表され、玉木代表と共に赤坂で街頭演説を行いましたが、正直なところ、この時点で「この党で活動していくのはもう難しいかもしれない」と思い始めていたと告白しました。
政治家としての責任、引き返せない状況
国民民主党の候補として単独で出馬会見を開くことになった6月10日よりも前から、山尾氏の国民民主党への気持ちは冷め始めていたことになります。しかし、公認内定の決定は既に受けており、一度出馬すると決めたことが世間にも知れ渡っていた以上、「自分から『やはりやめます』というのは、政治家として無責任な話です」と山尾氏は語ります。状況はすでに「自分から引き返すわけにはいかない」段階にあり、その後の無所属出馬へと繋がっていったのです。山尾氏の選挙戦は、党への疑問と政治家としての責任感の間で葛藤した結果の選択であったことが、今回のインタビューからうかがえます。
結論
山尾志桜里氏が参議院選挙に無所属で出馬し、落選に至った背景には、国民民主党の党運営に対する山尾氏自身の深い懸念と、公認発表を巡る党の対応への不信感がありました。特に、党が結党時の「中道政治」から逸脱し、ポピュリズムへと傾斜しているという山尾氏の見解は、今回の出馬の決断に大きな影響を与えたことが明確になりました。公認内定という既成事実と、政治家としての責任感から引き返すことができなかったという山尾氏の言葉は、その複雑な心情を浮き彫りにしています。この一連の出来事は、日本の政党における公認プロセスや、党と個々の政治家の理念の相違が、選挙結果にどのように影響を及ぼし得るかを示す事例と言えるでしょう。
参考文献
- デイリー新潮 (2025年7月28日). 山尾志桜里氏が明かす「国民民主党から公認取り消し」の全舞台裏「時すでに遅し、と思い始めていた」. 参照元: https://news.yahoo.co.jp/articles/fe2a6e995a8551733c893bbd647b950f79ee0296