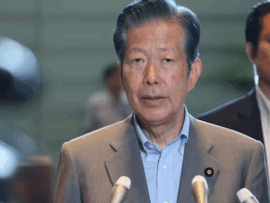デジタル化が進む現代において、私たちの生活に密着した健康保険証も大きな転換期を迎えています。従来の紙やプラスチック製の健康保険証は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」の活用を促進するため、昨年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。特に、7月31日には後期高齢者医療制度の健康保険証の有効期限が到来します。ご高齢の親を持つ方々にとって、これは見過ごせない重要な情報です。医療機関を受診する際の「持っていくもの」が変わる可能性があるため、今後の対応について正しく理解し、大切な家族に伝えておく必要があります。本記事では、健康保険証の切り替えに関する具体的な期限、マイナ保険証を持たない場合の対応策、そして知っておくべき「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」といった重要事項を詳しく解説します。
従来の健康保険証の有効期限と新しい医療受診体制
マイナ保険証への移行に伴い、従来の健康保険証は順次利用できなくなります。特に注目すべきは、7月31日を以て後期高齢者医療制度に加入している方々の健康保険証が有効期限を迎える点です。国民健康保険に加入している自営業者や退職者なども、自治体によって時期は異なりますが、7月31日以降に順次有効期限が切れます。一方、会社員が加入する健康保険組合、協会けんぽ、公務員が加入する共済組合については、保険証に期限の記載がなければ今年の12月1日が期限となります。
来たる8月1日以降、医療機関を受診する際には、原則としてマイナ保険証を利用することが求められます。これは、オンライン資格確認システムを通じて、より確実かつ迅速に保険資格を確認するための措置です。しかし、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証としての利用登録が未済の方も少なくありません。そうした方々が引き続き保険診療を受けられるよう、別の対応策が用意されています。
マイナ保険証がない場合の「資格確認書」とは?
マイナ保険証を所有していない、または利用登録が済んでいない場合でも、安心して医療機関を受診できるよう「資格確認書」が発行されます。この資格確認書は、従来の健康保険証と非常によく似た外見をしており、左上には「健康保険資格確認書」と明記されています。医療機関の窓口でこれを提示することで、これまで通り保険診療を受けることが可能です。
資格確認書は原則として申請なしで交付されますが、一部例外もあります。
-
申請なしで交付される人:
- マイナ保険証をお持ちでない方
- 後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上)
- ※混乱を避けるため、後期高齢者医療制度の加入者全員には、2026年7月末までの暫定的な措置として、申請不要で資格確認書が発行されます。
-
申請により交付される人:
- 高齢者や障害をお持ちの方で、マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診などが困難な場合
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
 期限切れとなる健康保険証のイメージ。マイナ保険証への移行で、特に高齢者の対応が求められています。
期限切れとなる健康保険証のイメージ。マイナ保険証への移行で、特に高齢者の対応が求められています。
「資格情報のお知らせ」の役割と注意点
資格確認書とは別に、「資格情報のお知らせ」という書類も存在します。これはマイナ保険証を既に保有している方々に送付されるものです。例えば、ご自身のマイナンバーカードを健康保険証として登録しているにもかかわらず、4月に保険者から紙のカードが送られてきた経験があるかもしれません。それが「資格情報のお知らせ」です。
この「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証が利用できない一部の医療機関を受診する際、マイナ保険証と併せて提示することで診療が可能となるものです。重要な注意点として、「資格情報のお知らせ」単体では保険診療を受けることはできません。必ずマイナ保険証(つまりマイナンバーカード本体)と一緒に携行し、提示する必要があることをご家族にも伝えておきましょう。
高齢の親を持つ家族が確認すべきポイント
今回の健康保険証の制度変更は、特に医療機関の利用頻度が高い高齢者の方々に大きな影響を与えます。もしご実家にご高齢の親御さんがいらっしゃる場合は、ぜひこの機会に、以下の点を確認してみましょう。
- 手元にマイナ保険証があるか?
- 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が届いているか?
- それぞれの書類がどのような役割を持つか理解しているか?
お盆休みなどの帰省時に、親御さんと一緒に手元にある健康保険に関する書類を確認し、今後の受診に備えることが大切です。万が一体調を崩した際に慌てることがないよう、事前に準備を整えておくことで、安心につながります。
結論
従来の健康保険証が順次利用期限を迎える中、マイナ保険証への移行と「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の適切な利用は、これからの医療受診において不可欠となります。特に高齢者の方々にとっては、制度変更への理解と準備がスムーズな医療アクセスの鍵を握ります。本記事で解説した内容を参考に、ご自身の健康保険証の状況、そして大切なご家族の状況を確認し、必要に応じてサポートしてあげてください。正確な情報を共有し、適切な手続きを行うことで、安心して医療サービスを受けられるようになります。
参考文献
- 厚生労働省: マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 政府広報オンライン: マイナンバーカードと健康保険証の一体化について