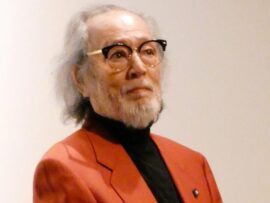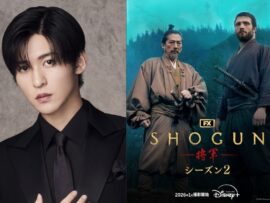トランプ米大統領は、貿易相手国・地域に対する新たな相互関税を8月7日に発動する大統領令に署名しました。これにより、4月に市場の動揺を受け一部撤回された高関税の「壁」が再び築かれることになります。「自国第一」を旗印に保護主義を強めるトランプ政権の姿勢は、日本経済にも直接的な影響を及ぼし、日本の税率も現行の10%から15%へと引き上げられます。国際的な自由貿易体制は、一段と退潮の危機に瀕しています。
「米国第一」主義の再燃:相互関税の「反撃」
トランプ大統領は、7月31日の大統領令署名に先立ち、SNSで「潮目は完全に変わった」と宣言し、高関税の復活が、米国の貿易赤字を拡大させてきた各国・地域への「反撃」であることを示唆しました。当初、約200カ国を対象にするとして早期の妥結に自信を見せていたものの、相互関税の停止期間中に進められた貿易交渉は思うように進まず、日本を含むわずか7件の合意に留まりました。大統領は「交渉相手が多過ぎる」と不満を漏らし、8月1日の期限ぎりぎりまで交渉を続けたものの成果は乏しく、最終的に関税発動へと舵を切る形となりました。米NBCニュースのインタビューでは、他国の対応が「遅過ぎる」と苛立ちを露わにしています。
新たな関税率は10~41%と、多くの国・地域で4月の相互関税率よりは低く設定されていますが、現状の基本税率である10%は上回る水準です。トランプ大統領は、今回の関税発動後も「4週間後に(交渉したいと)来ても、合意ができないという意味ではない」と述べ、将来的な税率引き下げに向けた市場開放などの提案による交渉を排除しない姿勢を見せています。
貿易交渉の「詰め甘さ」と日米合意の実態
今回の交渉合意内容には、食い違いや「詰め」の甘さが散見されます。例えば、対日合意に関してトランプ大統領は直接的な資金投入を念頭に「5500億ドル(約80兆円)の対米投資」を主張する一方、日本政府は企業への融資や融資保証の枠組みであると説明しています。この日米合意は、その後の欧州連合(EU)や韓国との交渉モデルになったとされ、関税率や対米投資の枠組み、自動車関税の引き下げなど、内容の多くが踏襲されました。しかし、対日本と同様に、米国と相手国の間で合意内容に関する主張の違いが見られました。
 ロサンゼルス港に停泊するコンテナ船:トランプ政権の相互関税発動が貿易量に与える影響
ロサンゼルス港に停泊するコンテナ船:トランプ政権の相互関税発動が貿易量に与える影響
新たな相互関税だけでなく、自動車関税の引き下げ時期が合意表明時点でも不明確な点も共通しています。7月31日夜、米政府高官は「商務省が関係当局と作業を進めているところだ」と述べました。自らが設定した交渉期限が迫る中、粗い内容でも合意を急ぐ米国の焦りが透けて見えます。
関税政策の「変容」:赤字削減から税収重視へ
高関税措置を「ディール(取引)」の手段として自国の貿易赤字削減を推し進めてきたトランプ大統領ですが、その狙いや関心は次第に関税収入へとシフトしています。米エール大予算研究所によると、米国の平均実効関税率は7月30日時点で18.4%に達し、これは1933年以来の高水準です。新たな相互関税の発動により税収はさらに増加する見込みで、大統領自身もこの日、「数千億ドルの関税収入を非常に迅速に獲得するだろう」と指摘しており、関税措置の長期化が一段と現実味を帯びています。
世界は1930年代に恐慌をきっかけに保護主義へと傾倒し、第二次世界大戦という悲劇を招きました。その反省から1947年に「関税貿易一般協定(GATT)」が締結され、戦後の自由貿易体制の礎が築かれました。しかし、トランプ政権は銅製品にも関税を発動し、さらなる措置も準備を進めています。「自国第一」の道を突き進むトランプ大統領は、なりふり構わず自由貿易の枠組みを揺るがし続けています。(ワシントン時事)
参考資料
- 時事通信社 (Jiji Press) – 元の記事リンク
- 米エール大予算研究所(Yale University Budget Institute)関連情報