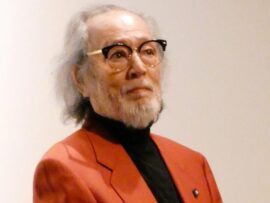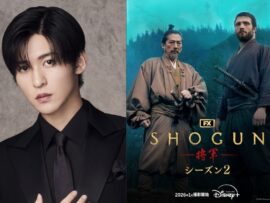日本社会は現状に「遅れている」という批判に直面していますが、他国もまた同様の課題を抱えています。Xで人気の谷本真由美氏(めいろま)が、世界のニュースから衝撃的な事例を紹介。移民増加によってイギリスで何が起こったのか、その教訓から日本が学ぶべき点を深く掘り下げます。
日印首脳会談:5万人受け入れ計画の波紋
今年8月、石破茂前首相とインドのモディ首相による日印首脳会談で、今後5年間でインドから日本へ5万人の熟練・準熟練人材を受け入れる「日印人材交流・協力アクションプラン」が署名されました。この計画は、両国間で今後5年間で50万人以上の人的交流を目標とし、そのうち5万人が日本のIT、製造、医療、介護分野の人材不足に対応する技能・専門人材となる予定です。これは単なる労働者派遣ではなく、官民連携の多層的な交流枠組みですが、日本に暮らす私たちはこの動向を注視する必要があるでしょう。
イギリスの「前例」:ブレグジット後の医療・介護現場
イギリスは、この人材受け入れ問題において「前例」となっています。ブレグジットによる東欧からの労働者減少やコロナ禍での医療関係者不足を受け、イギリスは海外から大量の医療・介護人材を招き入れました。2023〜2024年には、介護職およびホームケア従事者の外国人向けに7万件以上の就労ビザが発給され、その半数超がインド、ナイジェリア、ジンバブエ出身者でした。実に2023年だけで、外国人ケアワーカー向けの就労許可が約14万件、扶養家族が20万人で、合計30万人以上がわずか1年間でイギリスに移住したのです。
 医療サービスへの不安を示すイメージ写真
医療サービスへの不安を示すイメージ写真
質の低下と混乱:メーローマ氏の体験談
この大規模な受け入れは、国民に詳しく知らされないまま進行し、結果として質の低い医療・介護サービスが増加、現場環境は悪化しました。谷本氏の個人的な経験として、お子さんが目の病気で入院した際、アフリカ系の看護師が担当し、シーツや枕の提供拒否、清掃の怠慢など、東洋人を見下すかのような嫌がらせを受けたと言います。
日本が「標的」とされた背景と高市早苗氏への期待
なぜ日本が注目されたのか。アメリカではトランプ大統領によるH1-Bビザ取得費用の10万ドル(約1500万円)への改定により、アフリカや西アジア、南アジアからの出稼ぎがほぼ不可能となりました。そこで、新たな受け入れ先として日本が「目をつけられた」というわけです。谷本氏は、外国人雇用や移民対策を真剣に考える高市早苗氏が新首相になったことの重要性を指摘し、自身が暮らすイギリスと同じ過ちを日本には繰り返してほしくないとの強い思いを語っています。
まとめ
日本の深刻な人材不足に対し、外国人労働者の受け入れは不可避です。しかし、イギリスの経験が示すように、安易な受け入れは医療・介護サービスの質を低下させ、現場に混乱を招くリスクがあります。日本は、外国人雇用・移民対策において熟慮と周到な計画をもって臨むべきです。国民の理解を得つつ、持続可能で質の高い社会サービスを維持するための政策が今、求められています。