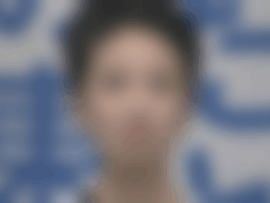激動する世界情勢の中、日本の未来を担う次世代の育成は喫緊の課題です。その基盤となる教育において、子どもたちの「志望校選び」は単なる個人の進路決定に留まらず、社会全体の人的資本形成に深く関わります。特に親と子、双方の願いと現実が交錯するこの問題は、しばしば親子の間に摩擦を生み、最良の選択を見失いがちです。本稿では、人気漫画『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生・土田淳真氏の洞察から、志望校決定における親の役割と、子どもが自ら未来を切り拓くための「最適なサポート」のあり方を深掘りします。
「親の感覚」がもたらすズレと情報格差
『ドラゴン桜2』では、桜木建二が難関大コースの生徒に対し、一方的に志望校を東大に変更すると宣言します。これは漫画内の極端な例ですが、現実の受験においても、親が子どもの志望校に深く関与することは少なくありません。しかし、親世代と子ども世代の間には約30年の隔たりがあり、この時間の経過は学校の評価、難易度、さらには教育方針に大きな変化をもたらしています。かつて名門とされた学校が現状ではそうではないケースや、その逆も珍しくありません。親のコミュニティ内で共有される過去のイメージや偏見が、最新の学校選びの妨げになることもあります。
志望校を選ぶ際には、偏差値という単一の指標に囚われず、共学か別学か、自由な校風か管理型か、伝統校か新興校か、自宅からの距離や通学時間など、多角的な視点から学校の特性を把握することが重要です。古い情報やイメージ先行の判断は避け、常に塾の先生など、最新かつ正確な学校や入試情報を持つ専門家から助言を得るのが賢明です。
 漫画『ドラゴン桜2』の表紙画像。東大合格請負人・桜木建二と生徒たちが志望校決定の重要性を説くシーンを表す
漫画『ドラゴン桜2』の表紙画像。東大合格請負人・桜木建二と生徒たちが志望校決定の重要性を説くシーンを表す
徹底した情報収集が未来を左右する
「どの学校も詳細に調べておくべき」という原則は、第何志望校であるかに関わらず当てはまります。特に見落とされがちなのが、毎日の通学手段に関する情報です。乗り換えの回数、始発かどうか、万が一の災害時に自力で安全に帰宅できるルートがあるかなど、受験ガイドブックや学校公式サイトには掲載されていない実践的な情報こそ、受験生の負担軽減と安心のために不可欠です。
筆者である土田氏の友人の実例は、この情報収集の重要性を痛感させます。彼は高校から中高一貫の男子校に入学しましたが、入学説明会の日まで男子校であることを知らなかったというのです。3年間通うことを考えると、これは笑い話では済まされない事態です。このようなリサーチ不足による悲劇を防ぐためにも、入念な事前調査が不可欠です。
子どもの主体性を育む「自己決定」の重要性
最も避けるべきは、子どもが「行きたくない」と感じている学校を無理やり受験させることです。この行為は、単に子どもの意思を尊重しないという倫理的な問題に留まりません。子どもに「親が決めたから、もし落ちても自分のせいじゃない」という他責思考を芽生えさせ、潜在的に全力を出さなくなる危険性を孕んでいます。仮に合格したとしても、「自分の成功は親のおかげだ。親に従っていればうまくいく」という依存的な思考を助長しかねません。
入学後の学校生活を実りあるものにするためには、子ども自身に「自分がこの学校を選んだのだ」という強い自己決定意識を持たせることが極めて重要です。この主体性こそが、困難に直面した際に自力で乗り越える力となり、将来にわたる成長の原動力となるのです。
進路選択は家族の協調作業、そして未来への投資
最終的に、志望校選びのプロセスで親に求められる最も重要な役割は、子どもの進路を最大限にサポートする姿勢です。受験結果が確定し、進学先が決まった以上、「あの時こうだったら」という後悔の念や「たられば」の言葉を親が口にすべきではありません。子ども自身が最もその感情を抱いているからです。
選んだ道が最善の道であると子どもに信じ込ませ、自信を持って進ませることこそ、親が果たすべき最後の、そして最も大切なサポートです。子どもの自律的な進路選択を支援し、適切な情報提供と精神的な支えを与えることは、個人の成長だけでなく、変化の激しい国際社会を生き抜く日本の未来への重要な投資と言えるでしょう。
参考文献
- 三田紀房, 『ドラゴン桜2』, 株式会社コルク
- 土田淳真, 「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」連載, ダイヤモンド・オンライン (Yahoo!ニュース記事の元記事として参照)