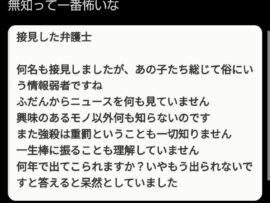オーストラリア政府は、2030年の運用開始を目指す海軍の新型フリゲート艦計画において、日本の三菱重工業が開発した「もがみ型」護衛艦の採用を正式に発表しました。これは、日本の防衛装備品の輸出としては画期的な事例であり、日豪両国間の安全保障協力が新たな段階に入ったことを示唆しています。「能力の要件と戦略的ニーズに迅速に対応できる最適な艦艇」と評価された「もがみ型」の導入は、インド太平洋地域における安定と秩序の維持に寄与すると期待されています。今後、日豪両国は、この新型フリゲート艦の共同開発を本格的に進めることになります。
オーストラリア海軍の新型フリゲート艦計画と「もがみ型」の評価
オーストラリアは、中国の海洋進出を強く意識し、老朽化したフリゲート艦に代わる新型艦11隻を導入する大規模な計画を進めてきました。この計画の予算は最大100億豪ドル(約9500億円)にも上り、昨年11月には共同開発国の最終候補を日本とドイツに絞り込んでいました。今回の選定で、日本が提案した海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」(もがみ型)をベースとした共同開発案が「最適な艦艇」として選ばれた形です。
 日本の海上自衛隊の最新鋭護衛艦「もがみ」型フリゲート艦。オーストラリア海軍が新型艦のベースに採用したことで、日豪の防衛協力がさらに深化する。
日本の海上自衛隊の最新鋭護衛艦「もがみ」型フリゲート艦。オーストラリア海軍が新型艦のベースに採用したことで、日豪の防衛協力がさらに深化する。
日本の防衛装備品輸出における歴史的意義
今回の「もがみ型」フリゲート艦の採用は、日本にとって完成品の防衛装備品輸出として、2020年のフィリピンへの三菱電機製防空レーダー輸出に続く2例目となります。近年、日豪両国は「準同盟国」としての位置づけを強め、安全保障面での連携を飛躍的に強化してきました。今回の共同開発は、その協力関係をさらに深める象徴的な出来事であり、国際社会における日本の防衛産業の信頼性と技術力の高さを示すものです。日本政府は、2024年11月に豪州が日本を最終候補に選定したことを受け、「防衛装備移転三原則」に基づき共同開発への参加を正式に承認し、防衛省は官民一体で推進する委員会を設置するなど、強力に売り込みを図ってきました。
「もがみ型」護衛艦の優れた特徴と国際連携への適合性
三菱重工業が開発した「もがみ型」護衛艦は、その革新的な設計と運用効率の高さが特徴です。特に注目されるのは、運用に必要な人員が従来型の約半数となる90人で済む点であり、これは長期的な運用コストの削減に大きく貢献します。また、豪州の同盟国である米国の艦艇と連携して運用しやすい設計が施されている点も、その大きな強みとして評価されました。多機能性を持ちながらも省人化を実現した「もがみ型」は、現代の海軍が直面する多様な脅威に対応するための理想的なプラットフォームと言えます。
ドイツ提案との比較と選定の背景
今回のフリゲート艦選定においては、ドイツのティッセンクルップ・マリン・システムズが提案した「MEKO A200」も有力候補でした。ドイツ案はコストが抑えられる点や、既存の戦闘システムを搭載できる統合性をアピールしていましたが、最終的には日本の「もがみ型」が選ばれました。豪ガーディアン紙は、日本案のより新しい設計が高く評価されたことに加え、2016年の豪州潜水艦受注契約で日本がフランスに競り負けた経緯があるため、豪州政府が「準同盟国である日本を再び失望させたくない」という思惑も背景にあったと報じています。
結論
オーストラリアによる日本の「もがみ型」フリゲート艦の採用は、日豪両国の防衛協力の歴史において重要なマイルストーンとなります。この決定は、日本の防衛装備品輸出の新たな扉を開くとともに、インド太平洋地域の安全保障環境における両国の役割を強化するものです。今後、共同開発が順調に進むことで、両国の戦略的パートナーシップはさらに深化し、地域の安定に不可欠な存在となるでしょう。
参考資料
- Yahoo!ニュース: オーストラリア、新型フリゲート艦に日本の「もがみ型」採用発表 共同開発へ