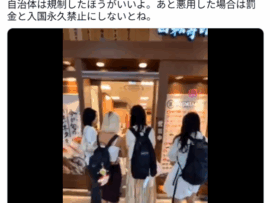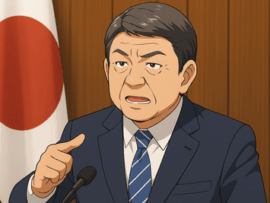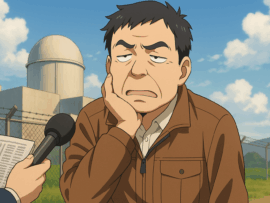日本の政局における「自民党分裂」の議論は、もはや机上の空論ではなく、現実味を帯びる重要な政治課題として注目されています。この議論は、単なる政党内の権力闘争に留まらず、日本の選挙制度の変遷と密接に関わりながら、有権者にとっての政治状況を大きく変えうる「政界再編」の起爆剤となる可能性を秘めています。本稿では、自民党分裂論の背景にある歴史的経緯と選挙制度の関係性、そしてそれが日本の政治にもたらす潜在的なメリットについて深掘りします。
日本の選挙制度の変遷と多党化の現状
戦後の日本政治では、衆院選や参院選の一部で長らく中選挙区制が採用されていました。この制度は、一つの選挙区から複数人が当選する方式で、結果として多様な意見が国会に反映されやすい一方で、政党内での派閥抗争を助長する側面もありました。しかし、1994年の公職選挙法改正により、衆院選には小選挙区比例代表並立制が導入されます。この改革は、イギリスのような二大政党制を日本でも実現し、政権交代可能な政治を目指すものと説明されました。
ところが、現実は当初の目論見とは大きく異なっています。二大政党制の確立には至らず、むしろ日本は政党が乱立する「群雄割拠」の状態にあると言えるでしょう。直近の参院選で議席を獲得した政党は11党に上り、衆院でも10党が議席を有しているのが現状です。ヨーロッパの多くの国では、イギリスを除いて二大政党制が機能している例は少なく、中小政党が連立政権を組むのが一般的です。日本においても、自民党と公明党の連立政権に、立憲民主党や日本維新の会などが加わる可能性も取り沙汰されており、二大政党制よりもヨーロッパ型の多党連立政権が現実味を増しているという指摘も専門家や識者から聞かれます。
自民党結党の経緯と「分裂」の現実味
自民党が1955年に誕生した経緯自体が、現在の分裂論に深く関連しています。当時、リベラル色の強かった自由党と、より保守色の強かった日本民主党が合併して成立したのが自民党です。この歴史的背景から、自民党は結党当時から「呉越同舟」や「同床異夢」の側面を常に抱えていました。つまり、党内には多様な思想や政策を持つ議員が共存しており、それが安定的な政権運営の基盤となってきた一方で、内部分裂の火種を常に内包していたとも言えます。
現在、この自民党の内部対立が表面化し、分裂が現実味を帯びているのは、その根深い党内構造に起因すると考えられます。もし実際に自民党が分裂した場合、リベラル志向の「新・自由党」が誕生すれば、石破茂氏や小泉進次郎氏といった政治家が参加することが取り沙汰されるでしょう。一方、保守色の強い「新・日本民主党」が形成されれば、高市早苗氏や小林鷹之氏といった面々がその中核を担うことが期待されるかもしれません。
 分裂後の「新・日本民主党」への参加が期待される高市早苗氏の肖像
分裂後の「新・日本民主党」への参加が期待される高市早苗氏の肖像
「政界再編」が有権者にもたらすメリット
ジャーナリストの鈴木哲夫氏は、自民党の分裂が「政界再編」の起爆剤として機能するのであれば歓迎するとの見解を示しています。氏によれば、政界再編が起きれば、有権者にとって非常に分かりやすい政治状況に変わる可能性があるといいます。
具体的には、自民党が分裂して生まれる保守色の強い新党に、日本保守党や場合によっては参政党などが加わり、明確な右派の政治グループが形成される可能性が指摘されています。また、自民党のリベラル派と立憲民主党の右派、公明党や国民民主党、場合によっては日本維新の会などが合流し、穏健保守・中道のグループが生まれることも想定されます。さらに、立憲民主党の左派を中心とし、共産党やれいわ新選組、社民党などもそれぞれのグループに参加することで、日本の政界が大きく分けて三つの主要な政治グループに再編されるシナリオも描かれています。鈴木氏は、このような再編が実現すれば、何よりも有権者が投票する際に、各政党やグループの立ち位置が明確になり、より自身の政治的志向に合った選択がしやすくなると強調しています。氏は大前提として、ヨーロッパ型の多党連立政権よりも、明確な二大政党制のほうが優れていると考えているとのことです。
結論として、自民党の分裂は、単なる既存政党の瓦解に留まらず、長らく課題とされてきた日本の政治状況の複雑さを解消し、有権者にとってより明瞭な選択肢を提供する「政界再編」へとつながる可能性を秘めています。これは、日本の民主主義をより健全なものにするための重要な一歩となるかもしれません。
参照元:https://news.yahoo.co.jp/articles/73d60bb78873203f489bf319bd4566c272c27c12