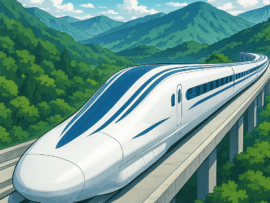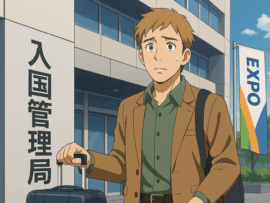太平洋戦争末期、日本本土への空襲が本格化したのは1945年に入ってからのことでした。もちろん、それ以前にも散発的な空襲はあり、1942年4月18日のドーリットル空襲が初めての本土空襲であったことは、広く知られています。しかし、当時の米軍は日本本土まで到達可能な爆撃機の開発に成功しておらず、またそのための拠点基地も確保できていませんでした。中国大陸や空母から爆撃機が出撃することはあっても、本格的に日本の都市を焼き尽くすような大規模な空襲は困難だったのです。
 B-29から見た東京、中央線三鷹駅周辺の俯瞰写真。1944年11月24日の初空襲で優先的に狙われたとされている武蔵野地域が写っている。
B-29から見た東京、中央線三鷹駅周辺の俯瞰写真。1944年11月24日の初空襲で優先的に狙われたとされている武蔵野地域が写っている。
本土空襲の転換点とB-29の登場
潮目が大きく変わったのは、1944年の夏に米軍がサイパン島やテニアン島を含むマリアナ諸島を制圧してからです。これにより、米軍はマリアナ諸島に巨大な航空基地を建設し、B-29による空襲は日本本土の大部分を射程圏内に収めました。そしてついに、日本中の都市の空にB-29が飛来するようになったのです。その始まりは、1944年11月24日にサイパンを飛び立った111機のB-29でした。この日、初めて東京上空に飛来したB-29の目的地は、東京都心ではありませんでした。彼らは都心の上空を通過し、現在の東京都武蔵野市、まだ田園地帯の面影が残っていた中央線三鷹駅の北側一帯を標的としたのです。
なぜ「三鷹駅の北側」が最初の標的となったのか?
現在の武蔵野の地は、閑静な郊外の住宅地という雰囲気を色濃く残しています。なぜB-29は、最初の空爆のターゲットにそのような場所を選んだのでしょうか。都心の住宅密集地を絨毯爆撃するような戦局ではまだなかったという判断からでしょうか。それとも、武蔵野に特別な軍事的・戦略的な何かがあったのでしょうか。この「最初の空襲」を受けた場所を訪れることで、その背景を探ります。
廃線跡をたどる空襲の記憶
中央線三鷹駅は、南側が三鷹市、北側が武蔵野市に分かれる市境の駅です。目的地は武蔵野市側、すなわち三鷹駅北口から出発します。駅前の広場からまっすぐに伸びる中央大通りを進むのも良いですが、今回はあえて遠回りをして向かいます。なぜなら、空襲のターゲットとなったその場所へは、かつて三鷹駅から引き込み線が通じていたからです。その廃線跡をたどれば、多少遠回りになっても道に迷うことなく目的地に到達できます。
引き込み線は三鷹駅の西側で北に分岐していました。ちょうど作家の太宰治が好んで利用したという有名な跨線橋があったあたりです。探し回るまでもなく、廃線跡はすぐに見つかります。現在そこには、美しい円弧を描く遊歩道と児童公園が整備されています。堀合(ほりあわい)児童公園・堀合遊歩道と名付けられたその場所こそが、かつての引き込み線の廃線跡なのです。この廃線跡を見失わないように進んでいけば、かつてB-29が狙った歴史的な場所へとたどり着くことができます。
結び
1944年11月24日、B-29が東京に初めて飛来した際、都心ではなく三鷹駅北側という特定の地域が標的とされた事実は、多くの人にとって意外な発見かもしれません。この歴史的な場所を実際に訪れ、現在の風景の中に隠された戦争の痕跡と当時の戦略を辿ることは、単なる過去の出来事としてではなく、生きた歴史として空襲の記憶を理解する上で非常に重要です。この地が「最優先」で狙われた理由を深掘りし、その歴史的背景を正確に知ることは、未来へと語り継ぐべき貴重な教訓となるでしょう。