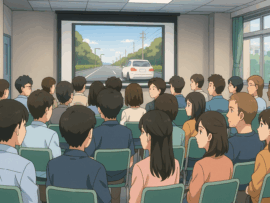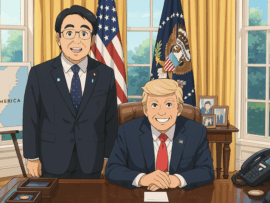先日、世間の注目を集めた座間9人殺害事件・白石隆浩死刑囚の極刑が執行されました。これは2年11カ月ぶりの死刑執行であり、法務省が公表を開始した1998年以来、最も長い空白期間を終えるものでした。この長期にわたる執行の停止には、袴田巌氏の再審無罪確定が少なからず影響していると考えられています。実際、内閣府の世論調査では、死刑制度の廃止を支持する割合が5年前の9%から約17%へと急増しており、国民の意識に変化が見られます。
刑事訴訟法では死刑確定から半年以内の執行が定められているにもかかわらず、2015年から2024年に執行された死刑囚の場合、その平均期間は9年を超えるという現状があります。この制度の厳格な運用がなされていないことに対し、批判の声も根強く聞かれます。近年では、死刑囚が拘置所内での処遇改善を求める訴訟も相次いでいます。例えば、大牟田4人連続殺人事件の死刑囚が養親との文通を許可されなかった件や、詐欺グループによるリンチ死亡事件の死刑囚が監視カメラのある居室に収容され続けたとしてプライバシー侵害を訴えた訴訟などが挙げられます。
果たして、死刑囚に対する国の処遇は適切なのでしょうか。その判断の一助となるのが、死刑囚が拘置所でどのような生活を送っているのかという実態を知ることです。彼らが日々の拘置所生活で何を考え、どのように過ごしているのかは、厚い壁に阻まれて表に出てくることはほとんどありません。しかし、過去に「週刊新潮」は、東京拘置所で死刑囚らの身の回りの世話をしてきた元「衛生夫」への独占インタビューを実施し、その秘められた実態を明らかにしています。当時の貴重な証言を再録し、死刑囚の処遇について深く考察する機会を提供します。
死刑囚を巡る制度と社会認識の乖離
「世間では、死刑囚は独居房の中で膝を抱え、死の恐怖に怯えながら、毎日、改悛の日々を送っている――そんなイメージを持っている人もいるかと思います。しかし、私が実際に見た死刑囚の姿とはかなりギャップがありました。その実態を明らかにすることで、死刑という制度を論じる際の材料にしていただければ、と考えたのです」。こう語るのは、かつて東京拘置所で衛生夫として数年間服役し、最近出所した30代の元男性です。
彼は、判決確定後、通常の刑務所に移送されるのではなく、「当所執行」という形で東京拘置所内で刑務作業に従事しました。東京・葛飾区小菅に位置する東京拘置所は、東京ドーム4個分という広大な敷地を持つ日本最大の拘置施設であり、通称「小菅」として知られています。中央には事務棟が筒状にそびえ、それを囲むように放射状にA、B、C、Dの4つの収容棟が立ち並び、未決囚、当所執行の受刑者、そして死刑囚が収容されています。
東京拘置所「死刑囚フロア」の日常
元衛生夫が担当したのは、4つの収容棟のうちの一つの上部階フロアでした。彼の主な仕事は、朝昼晩の食事の配膳と、担当フロアの清掃です。このフロアには両側に33房ずつ、合計66の独居房が設けられており、房には一つおきに収容者がいました。その入房者のほとんどが、死刑が確定した者か、一審または二審で死刑判決を受けた人々であり、まさに「死刑囚フロア」と呼べる空間でした。当時の東京拘置所には約70人の死刑囚が収容されており、このフロアだけでその半数近くを占めていたことになります。
 東京都葛飾区小菅にある日本最大級の東京拘置所外観。死刑囚や受刑者が収容される施設で、厳重なセキュリティ体制が伺える。
東京都葛飾区小菅にある日本最大級の東京拘置所外観。死刑囚や受刑者が収容される施設で、厳重なセキュリティ体制が伺える。
一般に想像される死刑囚の姿と、彼が実際に目撃した彼らの日常との間には大きな隔たりがあったと、元衛生夫は繰り返します。彼の証言は、外界から隔絶された拘置所の内部、特に最も秘密のベールに包まれた死刑囚の生活の一端を垣間見せる貴重なものです。
結論
本記事では、座間9人殺害事件の死刑執行を契機に高まる死刑制度への関心と、現状における制度運用上の課題、そして死刑囚の処遇に関する論争の背景を概観しました。特に、東京拘置所の元衛生夫による証言を通して、外部からはほとんど知られることのない死刑囚たちの拘置所での実際の生活、そして彼らの心理状態が、世間の抱くイメージと大きく異なる可能性があることを明らかにしました。
この限られた情報が、死刑制度そのものの是非、死刑囚の処遇の適正性、そして日本社会における司法のあり方について、読者の皆様が深く思考を巡らす一助となれば幸いです。本記事は前後編の前編であり、死刑囚たちの知られざる実態については、引き続き探求を続けます。
参考文献
- 「週刊新潮」2013年2月7日号
- ヤフーニュース(元の記事ソース)