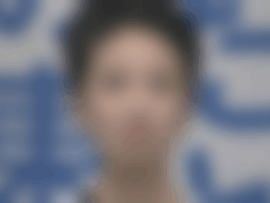現代社会において、多くの人々が「自分は周囲から浮いている」「集団の中でいつも余ってしまう」といった悩みを抱えています。特に人間関係が重視される日本の文化では、この「余り者」という感覚は自己肯定感を低下させる原因となりがちです。しかし、脳科学者・中野信子氏は、この「余り者」であることこそが、これからの時代における大きな価値となり得ると提言します。先日開催されたトークイベント「中野信子の人生相談」から、この重要なテーマに関する彼女の洞察をご紹介します。
「いつも自分だけ“余る”」33歳女性の悩み
CREA夏号とのコラボイベント「中野信子の人生相談」では、事前に募集された読者の悩みに対し、中野信子氏が生回答を行いました。その中でも特に会場の共感を呼んだのが、33歳会社員の女性から寄せられた「いつも自分だけ“余る”」という切実な相談でした。彼女は幼少期から体が大きく、学校では常に一人だけペアから外れたり、合コンや食事会、旅行といった場でもなぜか自分だけが「余り」になってしまう感覚が大人になっても続いていると打ち明けました。この長年の経験が自己評価に深く影響している様子が伺えました。
中野信子も共感「私も“余り者”でした」
この相談に対し、中野信子氏自身も「私も“余り者”でした」と共感を示しました。小学校で休むと先生が宿題を持ってきてくれるなど、周囲とは異なる経験をしてきたと語り、相談者の悩みに深く寄り添いました。中野氏は、この「“余り”にならないためにはどうすればいいか」という問いの本質は、むしろ「“余り”である自分を肯定できない」という苦悩にあると指摘。問題解決のアプローチを、他者からの評価に依存するのではなく、自己の内面と向き合う方向へと転換する必要があると示唆しました。
 脳科学者・中野信子氏が代官山蔦屋書店でのトークイベントで読者の悩みに耳を傾ける様子
脳科学者・中野信子氏が代官山蔦屋書店でのトークイベントで読者の悩みに耳を傾ける様子
日本の学校教育が「余り者」を生む構造
中野氏はさらに、なぜ日本社会、特に学校教育において「余り者」が生まれやすいのかを歴史的背景から分析しました。明治維新以降、日本の学校教育制度は欧米の教育モデルを範としており、その目的は国家運営のための「規格品」たる国民を育成することにありました。個々の子どもの特性や感情よりも、画一的な教育を通じて「規格品」を作り出すことが優先された結果、集団の枠に収まらない子どもたちは必然的に「余り」として扱われがちだったのです。しかし、中野氏は「“余り”であること、規格品として不適合であることは、その人自身の価値とはまったく関係ない」と強く語りかけました。
「はずれ値」こそが未来の価値になる
そして中野信子氏が提示した最も重要なメッセージは、「これからは『はずれ値』のほうが価値が高くなる時代」であるという点です。「規格品でない」人々こそが、AIでは代替できない創造性や問題解決能力を発揮できる可能性を秘めていると強調しました。均質性が求められた時代から、多様性と個性が尊重される時代へと移り変わる中で、「余り者」として感じていた特性は、むしろ独自の強みとなり得るのです。中野氏は、「“余り”であることは非常に価値が高いこと」だと断言し、そうした個性を「ぜひ誇りに思ってほしい。私も仲間です」と力強くエールを送りました。
まとめ
中野信子氏の人生相談は、「余り者」という一見ネガティブな経験を、未来における大きな価値へと転換する視点を提供してくれました。日本の教育や社会構造が時に生み出す「規格外」という感覚は、決して個人の欠陥ではなく、AI時代においてますます重要となる「はずれ値」としての個性であると認識すべきです。このメッセージは、自己肯定感を高め、自身のユニークな特性を強みとして受け入れる勇気を与えてくれるでしょう。自分は「余り者」だと感じているすべての人々へ、その個性こそが誇るべきものだという力強い肯定が送られました。