2025年7月の参議院選挙で突如として注目を集め、「極右政党が躍進」と国際的にも大きく報じられた参政党。その驚異的な伸長は、従来の新しい政党とは一線を画す独自の特性にありました。特に注目されるのは、潤沢な資金構造と、日本全国に緻密に張り巡らされた地方支部の存在です。短期間でなぜこれほど強固な党組織を確立できたのでしょうか?その鍵を握るのは、元日本共産党専従職員であり、参政党創立にも深く関わったジャーナリストの篠原常一郎氏です。篠原氏はインタビューに応じ、「実は参政党のモデルにしたのは、共産党と公明党です」と、その躍進の秘密を明かしました。
 参政党のスタッフが東京都江東区での街頭演説中にビラを配布している様子。
参政党のスタッフが東京都江東区での街頭演説中にビラを配布している様子。
篠原常一郎氏の経歴と参政党創設への関与
篠原常一郎氏は、1979年に18歳で日本共産党に入党し、25歳で専従職員となりました。2004年11月に党を除籍されるまで、長年にわたり選挙や政治の世界に深く関わってきました。その後、旧民主党で国会議員の政策秘書を務めた経験も持ち、現在はジャーナリストとして主に政治・軍事分野に関する情報をYouTubeで発信しています。
このような豊富な経験を持つ篠原氏が、2020年に参政党創設時の事実上の役員会であるボードメンバーに名を連ねていました。その経緯について、篠原氏は次のように説明しています。「参政党の神谷宗幣代表とは共通の知人がおり、『政党を作りたい』という話を聞きました。しかし、彼らは政党の構成方法が分からなかった。『篠原さんは共産党や民主党に在籍し、職員として支えてきた知見がある。その経験を生かしてアドバイスをしてほしい』と依頼されたのが始まりです」。
当初のボードメンバーには、YouTubeで活躍するKAZUYA氏なども名を連ねていました。篠原氏によると、彼らと共に合宿などで議論を重ねる中で、参政党の党の理念や綱領が作り上げられていったといいます。
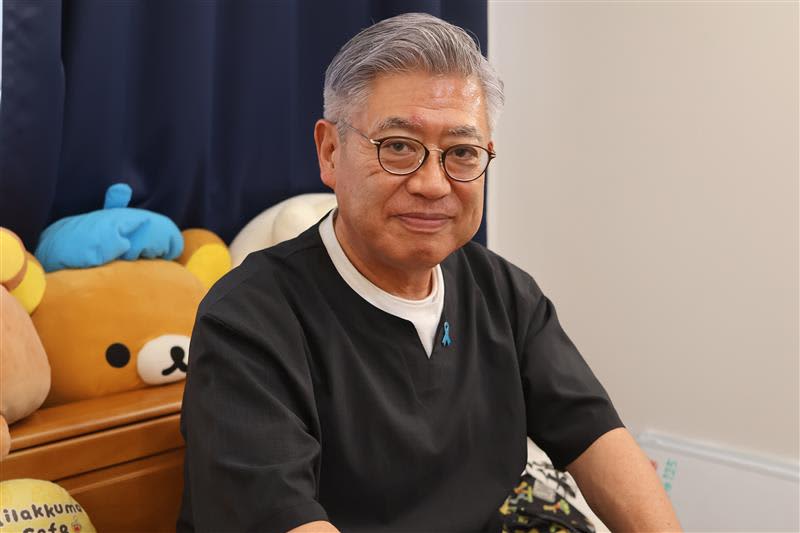 参政党の組織確立に貢献したジャーナリストの篠原常一郎氏が取材に応じている。
参政党の組織確立に貢献したジャーナリストの篠原常一郎氏が取材に応じている。
党の理念と綱領の形成:日本の自立への共鳴
参政党の創設メンバーたちが最も重視し、共通点を見出したテーマは「日本の自立」でした。篠原氏はこの点について、「一番の共通点は日本の自立、自主独立でした。それは、私自身が共産党にいた時代からのテーマでもあったのです」と語っています。
この「日本の自立」という理念は、参政党の綱領にも色濃く反映されています。綱領には、「天皇を中心に一つにまとまる平和な国をつくる」ことや、「日本国の自立と繁栄を追求する」といった文言が明記されており、これは彼らが目指す国家像の中核をなしています。
憲法9条と「自衛権」を巡る歴史的背景
篠原氏の念頭には、戦後すぐに日本共産党が前面に打ち出していた憲法9条への反対論がありました。日本国憲法制定前の1946年6月、共産党の野坂参三(後に議長、名誉議長などを歴任し、その後除名)は、「侵略戦争は認められないが、自衛戦争は認められるべきだ」と主張しました。これは「自衛権も認められない」とする当時の吉田茂首相との間で激しい論争を巻き起こしました。
憲法の採決日には、野坂参三が党を代表して以下のような反対意見を述べています。「我が国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする危険がある。それゆえに我が党は民族独立のためにこの憲法に反対しなければならない」。
 東京都新宿区でスマートフォンに表示された参政党のSNSショート動画。
東京都新宿区でスマートフォンに表示された参政党のSNSショート動画。
このような歴史的背景を念頭に、篠原氏らボードメンバーによる議論の末、参政党の綱領には「天皇を中心に一つにまとまる平和な国をつくる」「日本国の自立と繁栄を追求」といった理念が書き込まれました。彼らが目指す「自立した日本」の姿は、単なる政治スローガンではなく、歴史的な考察と議論の上に成り立っていることが示唆されます。
結論
参政党が短期間で強固な組織を確立し、2025年参議院選挙で躍進を遂げた背景には、元日本共産党職員であるジャーナリスト篠原常一郎氏の存在が不可欠でした。彼の経験と知見に基づき、日本共産党や公明党といった既存政党の組織モデルを取り入れたことが、地方支部ネットワークの構築と資金構造の確立に貢献したと分析できます。
また、「日本の自立、自主独立」という明確な理念を掲げ、歴史的な背景を踏まえた議論を通じて綱領を策定したことも、支持層の共感を呼ぶ大きな要因となりました。参政党の今後の政治活動と、それが日本政治に与える影響は、引き続き注目されるでしょう。






