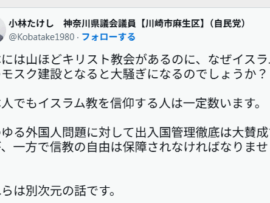衆参両院で少数与党となった石破政権という異例の政治状況下、野党第一党・立憲民主党が内閣不信任案の提出に慎重な姿勢を見せています。一部からは「弱腰」との批判もありますが、ジャーナリスト尾中香尚里氏は、その慎重さに合理的な理由があると指摘。内閣不信任案の持つ意味が変化し、立憲民主党の行動が「将来政権を担う政党」としての評価に直結しているからです。
臨時国会閉会と「弱腰」批判の背景
参院選後の臨時国会が閉幕し、石破政権は衆参両院で少数与党となりました。この異例の状況下、一部メディアは立憲民主党に内閣不信任案の提出を促し、野田佳彦代表の慎重姿勢を「衆院を解散されるのが怖いのか」といった「弱腰」と批判しました。
しかし、これは時代の変化を示唆します。「安倍一強」時代には「政治空白を招く」「無意味」と批判された不信任案の提出が、少数与党政権下では一転して求められるようになりました。これは、与野党の力関係の変化に伴う、不信任案への世論やメディア認識の大きな変容を示しています。
 日本の国会で議論が交わされる様子を示すイメージ画像:立憲民主党の役割
日本の国会で議論が交わされる様子を示すイメージ画像:立憲民主党の役割
少数与党政権下で変わる「内閣不信任案」の意義
少数与党政権の誕生は、立憲民主党にとって内閣不信任案の持つ意味を根本から変えました。石破政権下で国会内での相対的な力を増した立憲民主党は、もはや「万年野党」ではなく、「政権与党並み」に現実政治を動かす可能性を秘めています。
今後、立憲民主党の行動は「近い将来政権を担う政党にふさわしいか」という視点で国民に評価されます。そのため、不信任案の提出も「野党の安直な意思表示」では済まされず、戦略的な視点と政権を預かる覚悟が求められます。
「政権選択」は衆院選で、国益を損なわないために
参院選での立憲民主党の戦績が「横ばい」であったとしても、その側面のみを捉えることは、全体の政治状況を見誤り、国益を損なうリスクを伴います。内閣不信任案の提出は、広範な政治状況と立憲民主党の将来を見据えて熟考されるべきなのです。
尾中氏が指摘する通り、真の政権選択の場はあくまで衆議院選挙です。不信任案は政権信任を問う重要な手段ですが、政局混乱のためではなく、国民の負託に応える最終手段として慎重に用いるべきです。立憲民主党は目先の批判に動じず、将来の政権運営を見据えた責任ある行動を国民に示すことが求められています。
立憲民主党が内閣不信任案の提出に慎重なのは、少数与党政権下でその意味が大きく変化したためです。これはもはや「安直な意思表示」ではなく、政権を担う可能性のある党として、国民からの評価を意識した責任ある行動が求められています。真の政権選択は衆院選であり、同党には国益を見据えた戦略的な判断が期待されます。これが信頼される政党への脱却の道となるでしょう。