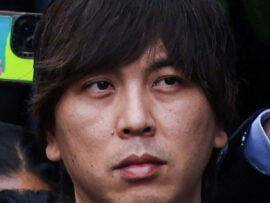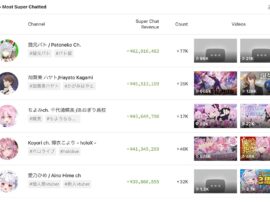日本マクドナルドが2025年8月9日から11日までの3日間限定で販売を予定していた「ポケモンカード付きハッピーセット」が、販売初日の9日には早くも多くの店舗から姿を消し、大きな波紋を呼んでいます。この早期品切れは、一般の消費者が購入した結果ではなく、いわゆる「転売ヤー」と呼ばれる転売を目的とした業者たちの大量購入が原因とされています。当初は転売ヤーへの批判が集中していましたが、現在はマクドナルド自身の対応への批判が巻き起こっており、企業の社会的責任が問われる事態へと発展しています。
 ポケモンカードとハッピーセットのパッケージ。転売問題が企業の社会的責任の議論を引き起こしている様子を示す。
ポケモンカードとハッピーセットのパッケージ。転売問題が企業の社会的責任の議論を引き起こしている様子を示す。
転売抑止策の限界と意図せぬ食品廃棄
今回のハッピーセット販売にあたり、マクドナルドは事前にいくつかの転売抑止策を講じていました。フリマアプリ大手のメルカリと連携して転売を抑制しようと試み、さらに一人あたりの購入数を5セットまでに制限。また、食べ残しをしないよう、利用客の良心に訴えるメッセージも発信していました。
しかし、これらの対策にもかかわらず、結果として大量のハッピーセットが転売され、さらにその食品部分が無断で廃棄されるという事態が多発しました。継続的に転売を営む場合、古物商許可が必要となるケースもありますが、転売行為そのものが法律で常に禁止されているわけではありません。しかし、地域社会との共生やフードロス低減を企業活動のPRポイントとしてきたマクドナルドが、皮肉にも自社のプロモーションを通じて食品廃棄という社会的問題を助長してしまった事実は、大きな批判の的となっています。純粋に商品を求めていた子どもたちやファンが購入できないという問題に加えて、企業イメージを損なう苦情が殺到する結果となりました。
マクドナルドに問われる「食」を扱う企業の責任
この問題を受け、マクドナルドは8月11日に公式文章を公表し、今後のより厳格な転売対策として、販売個数制限の強化、モバイルオーダー等での制限適用、そしてハラスメント行為を行う顧客への販売拒否などを発表しました。世間からの批判に迅速に対応し、対策を表明した点は一定の評価に値します。
しかし、この問題が浮き彫りにしたのは、転売ヤーの倫理観の欠如と、それに対する企業の責任です。転売ヤーにとって、1万円で取引される可能性のある商品(ポケモンカード)を、わずか1円で購入できるのであれば、ハッピーセットの食品部分を廃棄することは、ある意味で「経済合理性」がある行為と見なされかねません。もちろん、これが倫理的な行為でないことは明白ですが、倫理観に欠ける一部の人々は実際にそのような「合理的な」行動に及んでしまいました。その結果、インターネット上には「子どもが買えなかった」「利益を得たのは外国人転売ヤーばかりだ」「店員が見過ごしていた」といった声が溢れかえりました。
マクドナルドは、カード販売会社ではなく、あくまで「食」を販売する企業です。しかし、今回のプロモーションが、食品廃棄という反社会的な行動を意図せずとも引き起こしてしまったことは、企業としての社会的責任の範囲を改めて考えさせる契機となりました。
結論
今回のポケモンカード付きハッピーセットの転売問題は、単なる商品品薄や転売ヤー批判に留まらず、「企業の社会的責任」という広範なテーマを社会に問いかけました。特に、食料品を扱う企業が、プロモーション戦略によって意図せずフードロスや食品廃棄といった社会問題を引き起こしてしまった事実は重く受け止める必要があります。企業は、利益追求だけでなく、その活動が社会や環境に与える影響までを深く考慮し、持続可能な社会に貢献する視点を持つことが、今後ますます重要となるでしょう。今回の件は、企業のプロモーション活動がもたらす潜在的なリスクと、それに対する予見的な対策の必要性を示唆しています。