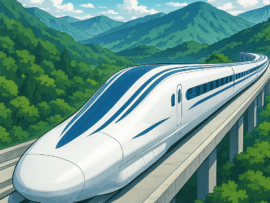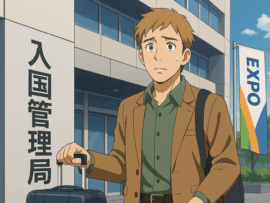福岡県が道路整備に伴う用地買収を巡り、当初算定した補償額の約5倍にあたる高値で土地を取得していた問題で、県は13日、記者会見を開き、複数の不適切な点があったことを認めました。県は今回の土地取得が不適切な用地買収であったと結論付け、地権者からの再検討申し出を受け、不動産鑑定士らの見解を踏まえて補償額を見直す方針を明らかにしました。この問題は、公費の適正な使用と行政の透明性に関わる重要な課題として注目を集めています。
 福岡県庁で記者会見を行う二場正義次長(右)と山口甲秀次長。不適切な用地買収問題について説明する様子。
福岡県庁で記者会見を行う二場正義次長(右)と山口甲秀次長。不適切な用地買収問題について説明する様子。
問題の用地と不適切買収の経緯
問題となっている土地は、福岡県赤村に位置する合計2505平方メートルの山林です。県道の整備事業の一環として、福岡県は2025年4月に、地権者である部落解放同盟福岡県連の副委員長の男性(75)と買収契約を締結。同年6月には、県から男性に対し、用地補償として総額2165万円が支払われました。
しかし、毎日新聞が入手した内部資料などから、県が買収交渉を開始した2024年10月の時点で、この土地の適正な補償額を430万円と算定し、提示していたことが判明しています。交渉を担当した県の出先機関である田川県土整備事務所は、地権者の男性が提示額を「安価だ」として難色を示したことを受け、2度にわたり委託業者に土地の評価をやり直させました。その結果、最終的には当初算定額の約5倍にまで価格がつり上げられていた経緯が明らかになりました。
価格高騰の背景と県の釈明
13日の会見には、県事務所を管轄する県土整備部の二場正義次長らが出席。「現地の状況を把握せずに2度にわたり、提示額を変更したことは適切ではなかった」と述べ、県の過失を認めました。
増額の主な要因は、山林の約半分(1099平方メートル)を「造成地」と評価し直し、これに整備費用などを加算したことでした。県事務所は、その評価見直しの際に、委託業者に対し「平米単価1万3700~1万4400円」とする「希望単価」を示し、造成費名目での加算を求めていたとされています。県は会見で、当初は山林価格で算定したものの、地権者から「山林ではない。宅地に近い」「坪単価2万~3万円が相場」などと主張されたため、2度の土地評価の見直しで増額したと説明しました。地権者の示す「相場」に沿うように「希望単価」を伝えたことについては、「参考として伝えた。(この値段に)近づけさせようとしたわけではない」と釈明しましたが、「今となっては不適切だった」と陳謝しました。
周辺相場との著しい乖離
委託業者は県の希望単価に沿って評価をやり直し、「造成地」を平米単価1万3900円と算定しました。さらに、県事務所はこれに3600円を上乗せし、最終的に「平米単価1万7500円」と決定しました。この造成地の価格は、周囲の土地と比較して著しく突出しています。福岡県が2024年に示した赤村の基準地価(住宅地、3カ所)は平米単価3800~6550円であり、最終算定額はその約4.6~2.6倍に相当します。また、周囲の宅地の標準的な取引価格である平米単価9000円(坪単価2万9752円)と比較しても、約1.9倍の高値となっていました。
県は会見で、この点についても「周辺の宅地価格よりも高額になっており、不適切だった」と改めて陳謝しました。一方で、増額の理由について「地権者の機嫌を損ねたくなかったわけではない。早期に用地交渉を妥結して速やかに発注したかったからだ」と述べ、地権者への「忖度」があったとの見方を否定しました。
再発防止策と今後の展望
福岡県は、今回の不適切な用地買収の再発防止策として、造成費を加味するなど特殊な算定を行う場合は、今後は出先機関だけでなく本庁と協議して決定するように制度を改める方針を示しました。
今回の問題は、行政における用地買収プロセスのずさんさや、公費の適正な使途に対する疑問を浮上させています。福岡県は補償額の見直しを約束し、再発防止策を打ち出しましたが、その実効性と今後の動向が注目されます。
参照
毎日新聞:https://news.yahoo.co.jp/articles/28a3dddee5dc0e0fb21b08e617e971911a330e6c