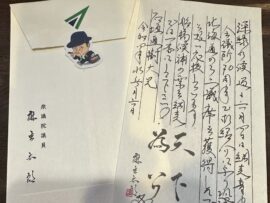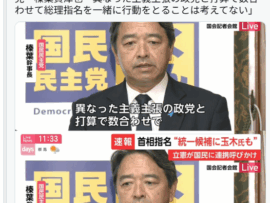地方の高速道路において、片側1車線による対面通行区間(暫定2車線)での事故は長年多発しています。特に、簡易的なラバーポールや黄線のみで車線が仕切られている箇所では、対向車線へのはみ出しによる正面衝突事故が頻繁に発生し、甚大な被害を招いています。2025年7月には徳島県で、車線を逸脱したトラックが高速バスに衝突する死亡事故が発生したばかりです。このような危険な状況が続くにもかかわらず、なぜ強固な中央分離帯の設置が進まないのでしょうか。その背景には、高速道路建設における「あくまで暫定」という特別な事情と、予算の制約が深く関わっています。
暫定2車線区間が抱える深刻な事故リスク
日本全国に広がる約1万4000kmの高速道路網(高速道路・自動車専用道などを含む)のうち、約3400km(有料区間1800km、無料区間1600km)が、簡易な対面通行形式の暫定2車線区間であることが国土交通省の資料で示されています(令和2年度時点)。これらの区間では、ドライバーが少しでも注意を怠れば、容易に対向車線にはみ出し、重大な正面衝突事故に繋がる危険性を常にはらんでいます。前述の徳島県での痛ましい死亡事故は、その典型的な例です。かつて全国を営業で走り回っていた筆者自身も、「これは危険だ」と感じた瞬間を何度か経験しています。このような状況への対策として、中央部をワイヤーロープやコンクリートで完全に分離する工事が有効とされていますが、その導入は思うように進んでいないのが現状です。
 簡易的なラバーポールで仕切られた暫定2車線の高速道路
簡易的なラバーポールで仕切られた暫定2車線の高速道路
全国に広がる暫定2車線と建設予算の壁
暫定2車線区間がこれほどまでに多い最大の要因は、高速道路建設における予算の制約にあります。多くの高速道路は最終的に4車線で計画されていますが、当初から全線にわたって4車線を建設しようとすると、建設費用が膨大になり、計画自体が立ち行かなくなる(予算が下りない)ケースが多々あります。高速道路の建設費用は「1kmあたり50億円」とも言われるほどの巨額を要するため、特に地方では「たとえ不完全であっても、とにかく高速道路を建設してほしい」という地域の切実な要望が強い傾向にあります。このような状況下では、初期建設費を抑えるために、将来的な拡張を見据えつつも、まずは片側1車線での暫定運用という妥協策が選択されがちです。
地方の切実な要望と工費節約の実態
地方自治体や住民にとって、高速道路の開通は地域経済の活性化や利便性の向上に不可欠であるため、建設費用の妥協は避けられない現実となっています。また、片側1車線ずつの道路を完全に別個に建設する場合、トンネルや橋梁といった大規模構造物もそれぞれ別に構築する必要が生じ、結果として工費の節約には繋がりにくいという課題があります。そこで採用されるのが、将来的な4車線化を見越して、まず「片側2車線分の幅員」で道路を建設し、その中央部を簡易的に仕切って上り・下り方向として暫定的に運用する方式です。これにより、トンネルや橋などの主要構造物は一度の工事で済み、初期費用を大幅に抑えることが可能となります。しかし、この工費節約の裏側で、ドライバーは依然として高い安全リスクに晒され続けているのが、暫定2車線区間の現状です。
課題を抱える暫定2車線区間の今後の展望
暫定2車線区間における事故多発の背景には、「あくまで暫定」という建設方針、膨大な建設費用、そして地方からの切実な高速道路建設要望という複数の要因が複雑に絡み合っています。これらの区間では、中央分離帯の不備が直接的な事故原因となることが多く、ドライバーの安全を確保するための根本的な対策が喫緊の課題です。今後の交通インフラ整備においては、建設費用の効率化と並行して、利用者の安全を最優先とする設計・改良が強く求められることでしょう。
参考文献:
- 東洋経済オンライン (記事提供元: Yahoo!ニュース)