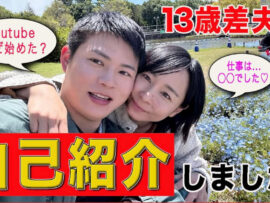1945年8月15日、太平洋戦争は終結を迎えました。しかしその直前、ソ連軍が旧満州へと侵攻を開始。現地の日本人開拓民の中には、終戦後もなお想像を絶する状況下での逃避行を強いられ、本土への帰還に長い年月を要した人々がいました。彼らが那須の地に築き上げた集落「栃木県那須町千振」は、その過酷な歴史と不屈の精神を今に伝える場所です。本稿では、地方自治ジャーナリスト葉上太郎氏の著書『47都道府県の底力がわかる事典』を基に、千振集落の知られざる歴史と、そこに息づく人々の絆に迫ります。
天皇陛下が二度も訪問した「千振」集落の特別な意味
平成の天皇陛下が、終戦60周年と70周年の節目に二度も訪問された土地が、栃木県那須町の千振(ちふり)です。この地は、中国東北部、通称「旧満州」から引き揚げてきた人々が、那須山麓に懸命に開拓した特別な集落として知られています。全国各地の引き揚げ者集落が時代の流れと共にその開拓色が薄れていく中で、千振はなぜこれほどまでに強固な団結力を維持し続けてきたのでしょうか。その答えは、戦前の歴史に遡って紐解く必要があります。
 旧満州引揚者により開拓された那須町千振集落の風景。過酷な歴史を物語る
旧満州引揚者により開拓された那須町千振集落の風景。過酷な歴史を物語る
満州開拓の「模範」とされた千振開拓団の成立背景
1932年、日本は中国東北部を占領し、傀儡国家である満州国を建国。日本の農村部からは大量の開拓移民が送り込まれました。その中でも、七虎力(チーフーリー)に入植したのが、後の千振開拓団となる人々です。当初、彼らは抗日勢力などに対抗するため、14県から選抜された約500人の在郷軍人らが武装して開拓に当たっていました。開拓初期には戦闘による犠牲者も出ましたが、宗光彦初代団長が現地の人々との「融和」を強く図ったことで、千振開拓団は「満州開拓の手本」とまで言われるようになります。団員たちは日本から家族や結婚相手を呼び寄せ、出身県ごとに集落を形成し、新たな生活基盤を築いていきました。
終戦直前のソ連侵攻と、引き揚げの悲劇
しかし、その穏やかな生活は突如として終わりを告げます。1945年8月9日、終戦わずか6日前のことでした。旧ソ連軍が満州に侵攻し、開拓団に避難命令が出されたのは8月11日。避難列車が運行されたものの、16歳から45歳の男性はすでに動員され、吉崎千秋第二代団長や太田宗次郎副団長ら約100人が千振を離れていました。残された約1200人の家族は、約3分の1が列車に乗り遅れたり、残留を決断したりする選択を迫られます。特に悲劇的だったのは、残留を選んだ宮城集落の81人が追い詰められ、集団服毒自殺に至ったことです。乗り遅れた人々は、中島澄子さん(95)のように徒歩で逃げ惑うこととなりました。彼女は現在の千振集落の最長老の一人であり、天皇陛下とも面談された方です。
まとめ
栃木県那須町千振の歴史は、旧満州からの過酷な引き揚げ、そして新たな土地での懸命な開拓という、日本の戦後史の一断面を色濃く映し出しています。天皇陛下が二度もこの地を訪れた事実は、千振集落の人々が経験した苦難と、それを乗り越えて築き上げた団結の深さ、そして平和への願いがいかに重要であるかを物語っています。中島澄子さんのような証言者の存在は、歴史の記憶を次世代に繋ぐ貴重な橋渡し役であり、千振の物語は、日本の過去から学び、未来を築くための大切な示唆を与えてくれるでしょう。
参考文献
- 葉上太郎 著『47都道府県の底力がわかる事典』