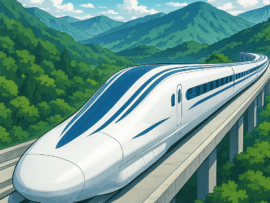日本の10代にとって、「大学受験」は人生における最も大きな節目の一つと言えるでしょう。残念ながら、現状の日本社会では、いわゆる「良い大学」に進学することが、将来の職業選択の幅を広げ、希望するキャリアを実現する可能性を高める傾向にあります。それほどまでに、大学受験が持つ影響力は計り知れません。このような複雑な時代において、「自分らしい大学進学」を果たすための指針となる書籍『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が出版されました。この書籍は、きれいごと抜きに「大学受験とは何か」「人生とは何か」を深く考察できる、まさに受験の決定版です。本記事では、発刊を記念して、著者であるびーやま氏への特別インタビューをお届けします。
MARCHは本当に「賢くない」のか?データが示す実力
人気大学群として知られるMARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)ですが、一部では「MARCHは知名度があるだけで、賢くはない」といった意見も聞かれます。この点について、びーやま氏は明確に否定しています。彼は、「MARCHは賢くないというのは言い過ぎです」と述べ、多くの意見がある中でも、偏差値のデータを見ればMARCHよりも高い大学の方が少ない現状を指摘。「MARCHを賢くないと言ってしまうのはさすがに無理がある」と語ります。これは、客観的な学力指標から見て、MARCHが依然として高いレベルを維持していることの証左であり、決して「知名度だけ」ではない実力があることを示唆しています。
「知名度先行」はデメリットか?競争を生むブランド力
しかし、そうした声の背景には、MARCHが持つ「知名度が先行している」という認識があることも事実です。この点に関して、びーやま氏は「知名度が先行することは別に悪いことではない」という自身の考えを述べています。大学が持つ知名度が高いからこそ、多くの受験生やその保護者が興味を持ち、志願者が増加します。この志願者の増加こそが、大学内の競争を激化させ、結果として高いレベルの教育や研究環境が維持される原理に繋がるのです。
 大学受験や進路について考える学生のイメージ
大学受験や進路について考える学生のイメージ
びーやま氏は、「知名度のあるMARCHに進学したい!」と多くの学生が願うことで初めて、MARCHの教育レベルやブランド価値が維持されると解説しています。この視点から見ると、知名度は単なる認知度ではなく、大学の質を向上させるための重要な要素であることが理解できます。名声が競争を促し、それがまた新たな優秀な学生を引きつける好循環を生み出しているのです。
推薦入試による「学力低下」論争の真実:多様な才能の発見
MARCHに限らず、近年、推薦入試などによる大学全体の「学力レベルの低下」が頻繁に議論されることがあります。これに対し、びーやま氏は「学力低下はもしかするとあるかもしれない」としながらも、現在の推薦入試は「ルールを破っているわけではない」と強調しています。目の前にある受験のチャンスを、定められたルールに則って掴んだ学生は、ある意味で「頭がいい」と評価することもできると彼は語ります。
これは、単に一般入試の学力基準だけで学生を測るのではなく、多様な能力や可能性を持つ学生を受け入れるという、大学が担う「才能の発掘」という役割の重要性を指摘しています。もし全ての学生を一般入試だけで選抜すれば、平均的な学力は上がるかもしれませんが、特定の分野で際立った才能を持つ学生や、ポテンシャルを秘めた学生を見落とす可能性も出てくるでしょう。びーやま氏の意見は、多様な入試制度が持つ意義と、それを通じて大学が社会に貢献する側面があることを示唆しています。
まとめ:MARCHの価値と多角的な大学選びの視点
本記事では、びーやま氏への特別インタビューを通じて、大学受験におけるMARCHの真価と、それを取り巻く様々な議論について深掘りしました。「MARCHは賢くない」「知名度だけ」といった意見は、客観的なデータや大学の役割を多角的に見れば、必ずしも的を得ているとは言えないことが明らかになりました。
MARCHは、その高い偏差値が示す通り確かな学力を持つ難関大学群であり、その知名度は健全な競争を生み出し、大学のレベル維持に貢献しています。また、推薦入試などの多様な選抜方法は、学力だけでなく、学生の多様な才能や可能性を発掘するという大学の重要な役割を果たす上で不可欠であると言えるでしょう。
受験生や保護者の皆様には、一方向的な情報に惑わされず、データに基づいた事実と、大学が社会に果たす多角的な役割を理解した上で、ご自身の将来に最適な進路選択をしていただくことを推奨します。
参考文献
- びーやま (2024). 『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』
- Source link: Yahoo!ニュース