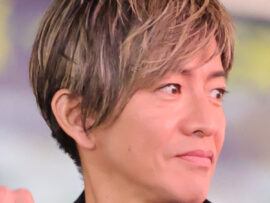参院選で初当選を果たした社民党のラサール石井氏(69)が、ジャーナリストの桜井よしこ氏による「南京大虐殺」に関する発言に対し、自身のX(旧ツイッター)を通じて疑問を呈しました。この歴史的出来事を巡る議論は、日本の歴史認識、報道の役割、そして政府の公式見解に改めて注目を集めています。今回は、ラサール氏の発言の背景にある桜井氏の主張、そしてこの問題に対する日本政府の公式見解と日中歴史共同研究の報告を詳しく掘り下げていきます。
ラサール石井氏の発言と桜井よしこ氏の主張
桜井よしこ氏は、産経新聞のコラムにおいて「『南京大虐殺』はわが国の研究者らによってなかったことが証明済みだ」と主張しました。これに対し、ラサール石井氏は「櫻井よしこ氏『南京大虐殺はなかったことが証明済み』発言に疑問続出…専門家は『あったと結論が出ている』と否定」と題された記事を引用し、「『言ったもん勝ち』か。では、証明された論文を示して欲しい」と強く反論。情報の根拠を求めました。
 参院選で初当選後、南京大虐殺に関する発言に言及する社民党のラサール石井氏
参院選で初当選後、南京大虐殺に関する発言に言及する社民党のラサール石井氏
さらにラサール氏は、この記事を校閲した産経新聞も桜井氏と同じ見解であれば、同様に証明を提示すべきだと指摘。「『石破氏辞任』の号外を出した読売といい、二誌は新聞である事を放棄したのか。政治家の走狗となるな」と述べ、大手新聞社の報道姿勢に対しても警鐘を鳴らしました。この発言は、歴史認識を巡る議論が、メディアの信頼性や政治との関係性にも及ぶことを示しています。
日本政府の公式見解:「南京事件」の否定はせず
「南京大虐殺」に関する日本政府の公式見解は、「南京事件」という表現で示されています。政府は、「日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない」と考えています。この見解は、事件の存在自体を認めるものであり、歴史的事実として重要な意味を持ちます。
一方で、政府は「被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難である」とも表明しています。これは、事件の規模や犠牲者数に関する議論が複雑であり、様々な歴史的資料や研究に基づいた異なる推計が存在するという現実を反映しています。政府の見解は、事件の発生を認めつつも、その詳細な解釈については慎重な姿勢を示していると言えるでしょう。
日中歴史共同研究が示す「南京虐殺事件」の実態
2006年、当時の安倍晋三首相の訪中時に合意され、日中両国から各10人の有識者計20人が参加して立ち上げられた日中歴史共同研究でも、「南京事件」は「南京虐殺事件」と表記され、その実態について詳細な報告がなされています。
同研究では、「日本軍による捕虜、敗残兵、便衣兵、及び一部の市民に対して集団的、個別的な虐殺事件が発生し、強姦、略奪や放火も頻発した」と結論付けられています。この記述は、日本軍による残虐行為があったことを明確に認めるものです。犠牲者数については、極東国際軍事裁判の判決で20万人以上(松井司令官への判決文では10万人以上)、1947年の南京戦犯裁判軍事法廷では30万人以上とされ、中国側の見解は後者の判決に依拠しています。一方、日本側の研究では20万人を上限として、4万人、2万人など様々な推計がなされていることが指摘されています。
このように犠牲者数に諸説がある背景には、「虐殺」(不法殺害)の定義、対象とする地域・期間、埋葬記録、人口統計など、資料に対する検証方法の相違が存在すると説明されています。共同研究は、単に事実を列挙するだけでなく、歴史認識の違いが生じる根源にも踏み込んでいます。
結論
ラサール石井氏が桜井よしこ氏の「南京大虐殺はなかった」という発言に異議を唱えた一連の動きは、依然としてこの問題が日本の社会においてデリケートかつ重要な歴史認識のテーマであることを浮き彫りにしました。日本政府の公式見解や日中歴史共同研究の結果が示しているのは、犠牲者数に諸説あるものの、日本軍による非戦闘員の殺害や略奪行為といった「南京事件」の発生自体は否定できないという認識です。
真摯な歴史対話と、客観的な事実に基づいた理解の探求は、今後も日本の国内外における信頼関係構築のために不可欠な課題であり続けるでしょう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース (記事元)