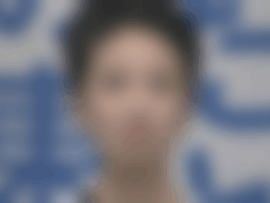永井豪先生が原作を手掛けた不朽の名作『デビルマン』(1972年)は、発表から半世紀以上が経過した現在も、漫画版は多くの読者に親しまれています。しかし、同時期にテレビ放送されたアニメ版については、その独特の結末から「打ち切りだった」という誤解が根強く残っています。実際には、アニメ版の結末は制作上の意図に基づいたものであり、永井豪作品における「完結」の一つの形を示していると言えるでしょう。
アニメ『デビルマン』誕生秘話:『魔王ダンテ』から独立した二つの作品
アニメ『デビルマン』の制作経緯には、意外と知られていない事実があります。元々は東映動画(現・東映アニメーション)が、永井先生の漫画『魔王ダンテ』のテレビアニメ化を企画したことが発端でした。しかし、この企画は途中で変更され、全く新しい作品として『デビルマン』が生み出されることになります。東映側からの依頼を受け、永井先生があらためて原作を描き下ろしたことで、漫画版『デビルマン』が誕生しました。
このため、アニメ版が漫画版の直接的な原作であるというわけではありません。永井先生自身も、アニメと漫画の関係について「同一の基本設定を使用して描かれた2つの作品」であるとコメントしています。つまり、ヒーローものとして明確な決着を目指したアニメ版と、ホラーから黙示録的な結末へと向かう漫画版という、それぞれのメディア特性に合わせた展開となったのです。
 1972年放送開始のアニメ『デビルマン』DVD第1巻のパッケージ。永井豪による名作の衝撃的な最終回を巡る考察。
1972年放送開始のアニメ『デビルマン』DVD第1巻のパッケージ。永井豪による名作の衝撃的な最終回を巡る考察。
魔王ゼノンを倒さずに幕引き?アニメ版『デビルマン』の異例の最終回
アニメ版『デビルマン』は、独自のストーリー展開で最終回を迎えました。最後の敵は、魔王ゼノンの親衛隊長であり、デビルマンの元上司でもある妖獣ゴッドとの戦いです。この最終回が全国で放送されたわけではなく、関東圏など一部地域では、その1話前の第38話「妖獣ドリムーン 月は地獄だ」で終了したという背景もあります。
ここで疑問となるのは、『デビルマン』という作品が、ラスボスである魔王ゼノンを倒さずに最終回を迎えている点です。漫画版とは異なり、ヒーローものとして描かれたアニメ版であれば、魔王ゼノンを打ち倒してハッピーエンドを迎えることも可能だったはずです。この異例の結末には、当時漫画版の連載がまだ続いていたことが影響している可能性も考えられます。漫画の展開とアニメの結末が乖離しすぎるのを避ける意図があったのかもしれません。
「当面の敵を倒す」スタイル:『デビルマン』後番組にも見られる共通点
興味深いことに、『デビルマン』の後に放送された『ミクロイドS』(1973年)や『キューティーハニー』(1973年)といった永井豪先生原作のヒーロー作品にも、同様の傾向が見られます。これらの作品もまた、ヒーローものでは定番であるはずの悪の組織を完全に壊滅させることなく、当面の敵を倒しただけで最終回を迎えているのです。
なぜこのような終わり方が繰り返されたのでしょうか。そこには、単なる予算やスケジュールといった制約だけでなく、時代を先取りした意図があったのかもしれません。悪の組織の根源を倒しきらないことで、物語に余韻を残し、その後の展開やメディアミックスへの可能性を示唆する、あるいは固定された「完結」の概念にとらわれない、新しいヒーローものの形を模索していたとも考えられます。
永井豪作品が示す「終わらない」完結の哲学
アニメ『デビルマン』の最終回が「打ち切り」と誤解されがちですが、その実態は、制作背景や当時の他作品との比較から、意図的な「完結」の形であった可能性が高いと言えます。魔王ゼノンを倒さずに物語を締めくくるスタイルは、その後の永井豪作品にも見られる共通の傾向であり、ヒーローと悪の組織の戦いには常に終わりがなく、形を変えて続いていくという、奥深いメッセージを内包していたのかもしれません。こうした「当面の敵を倒して完結」という形式は、永井豪先生が提示した、既存の物語構造に囚われない、ある種「開かれた」作品世界への試みであったとも解釈できるでしょう。