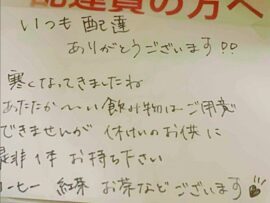夏休みが終わり、子どもたちが新学期を迎える一方で、学校現場では「保護者対応」が教職員にとって計り知れない負担となっています。近年、教員を精神的に追い詰める「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が深刻化し、教員の離職や病休の増加に繋がっています。先日、東京・立川市で発生した保護者同行者による教員への暴行事件は氷山の一角に過ぎず、日常的に教員が直面する精神的プレッシャーは計り知れません。教職員を守る仕組みが脆弱な現状は、日本の教育の未来を脅かす緊急の課題として、早急な見直しが求められています。
「些細なこと」が「大きな負担」に:現場教師の生の声
教育研究家の妹尾昌俊氏は、「小学生の子どもがちょっとケガしたくらいで学校から保護者に電話をかける必要はない」と提言しますが、実際には「なぜちゃんと教えてくれなかったのか」と感情的なクレームを受けるケースが後を絶ちません。多くの教職員が、全体のごく一部の「ややこしい保護者」への対応に、エネルギーの99%を奪われていると語ります。ある小学校の教頭は、「昨夜、保護者が3時間にもわたり怒鳴りつけてきた」と疲弊した様子で報告しました。また、「保護者から電話で1時間以上お説教され、反論すれば火に油を注ぐため、ひたすら聞くしかない。耳も肘も痛くなった」という悲痛な声も聞かれます。このような長時間にわたる一方的な苦情は、教職員の心身を蝕み、精神疾患を抱える教員の増加に直結しています。
 保護者対応が高ストレス要因となる教員の現状を示すグラフ
保護者対応が高ストレス要因となる教員の現状を示すグラフ
「カスハラ対策」が遅れる学校現場の現実
一般社会ではカスハラ対策への意識が高まり、多くの企業や保育園などでは、カスハラ防止の注意喚起文書が配布され、具体的な対策が講じられています。しかし、公立小中学校の現場では、「嫌なら別の学校に行ってください」と悪質な保護者に対しても対応を断ることができません。その結果、「傾聴が重要」「保護者の怒りが子どもに向かってはいけない」といった配慮が過度に重視され、最前線の学級担任や学年主任、教頭、校長らが、ひたすら我慢を強いられながら粘り強く対応せざるを得ない状況が続いています。この状況は、教職員の過度なストレスを生み、本来の教育活動に集中することを困難にしています。教職員の精神的健康を保護するための仕組みが極めて弱く、これが教員の離職率増加や、質の高い教育提供への支障となっているのです。
教職員の心身を守るための明確なガイドラインと法的な保護が不足している現状は、早急に改善されるべきです。教育現場におけるカスハラ問題は、個々の教員の問題に留まらず、日本社会全体の教育の質と未来に関わる喫緊の課題と言えるでしょう。夏休み明け、子どもたちだけでなく、先生たちもまた、重い足取りで新学期を迎えているのではないでしょうか。
参考文献:
- 東洋経済education × ICT. 「保護者から電話で1時間お説教も…」Yahoo!ニュース, 2023年8月26日掲載.
https://news.yahoo.co.jp/articles/2fd56ea30e86426e4dc146914b663405d48a223f