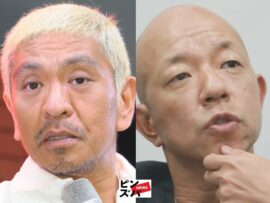プラスチックによる地球規模の環境汚染が深刻化する中、「プラスチック条約」策定に向けた国際的な議論が活発化しています。先日行われた国際会議では、プラスチックの“生産量規制”導入を巡り、EUや太平洋の島しょ国が積極的な姿勢を示す一方、石油産出国からは強い反対意見が出され、合意には至りませんでした。こうした各国の足並みの不揃いが続く中、最新の研究では、微細化した「マイクロプラスチック」が環境中だけでなく、心臓や肺といった人体にも取り込まれ、健康への影響が示唆されていることが明らかになっています。マイクロプラスチック研究の第一人者である東京農工大学の高田秀重名誉教授が、その最新動向を語ります。
 マイクロプラスチック汚染と国際的なプラスチック条約策定に向けた議論の様子
マイクロプラスチック汚染と国際的なプラスチック条約策定に向けた議論の様子
プラスチック汚染の現状とマイクロプラスチックの正体
ペットボトル、包装容器、化学繊維、自動車のタイヤなど、私たちの日常生活はプラスチックに深く依存しています。世界では年間約4億トン以上ものプラスチックが生産され、これは原料となる石油産出量の8〜10%に相当する膨大な量です。自然環境中に放出されたプラスチックは、紫外線や物理的衝撃により劣化し、5ミリメートル以下の微細な欠片へと砕かれていきます。これが「マイクロプラスチック」と呼ばれる物質です。年間170万トンものプラスチックが適切に処理されずに環境中へ流出し、その結果、世界中の海洋、河川、土壌、さらには大気中からもマイクロプラスチックが検出されています。
日本におけるマイクロプラスチック汚染:身近な河川からの警告
人間の生活とプラスチックが密接な関係にあることから、東京や大阪のような人口密集都市圏では、環境中に放出されるプラスチック量が特に多い傾向にあります。東京理科大学の研究チームの調査によると、多摩川水系では年間約72トン、淀川水系では年間約92トンものプラスチックごみが河川清掃活動によって回収されています。これらのデータは、日本の都市部におけるプラスチック汚染の規模と、それがマイクロプラスチックとなって環境に与える影響の深刻さを物語っています。
人体への侵入経路と健康への示唆
マイクロプラスチックの検出は、もはや環境中に限定される話ではありません。肺、胎盤、心臓、そして血液中など、ヒトの体内のほぼすべての主要臓器からマイクロプラスチックが見つかっています。人体への主な取り込み経路としては、プラスチック製の食器を使った食事の際に生じる微細な小片の摂取や、河川・海洋環境中のプラスチックを取り込んだ魚介類を食べる行為が挙げられます。さらに、大気中や飲料水中からのマイクロプラスチック検出例も多数報告されており、これらを通じた人体への侵入も十分に考えられます。専門家は、これらの体内への蓄積が長期的に健康へ与える影響について、更なる研究の必要性を指摘し、その示唆に富む結果が注目されています。
「プラスチック条約」策定に向けた国際社会の葛藤
国際社会は、この深刻なプラスチック汚染を食い止めるため、「プラスチック条約」の策定を目指していますが、その道程は容易ではありません。条約の重要な焦点の一つである“生産量規制”を巡っては、環境保護を強く訴えるEU諸国や太平洋の島しょ国が積極的な姿勢を示す一方で、プラスチック原料となる石油の産出国からは根強い反対の声が上がっています。この意見の対立により、直近の国際会議では具体的な合意には至らず、今後の協議の行方が注目されています。国際的な協力体制の構築と、各国の利害調整が、条約の実効性を左右する鍵となります。
結論
マイクロプラスチック問題は、環境汚染に留まらず、私たちの健康にまで影響を及ぼす喫緊の課題です。日常に溢れるプラスチックの利便性と引き換えに、見えない形で人体への影響が懸念される中、「プラスチック条約」の策定は待ったなしの状況と言えます。国際社会が直面するこの複雑な課題に対し、日本を含む各国が連携し、生産・消費・廃棄のサイクル全体を見直すことで、持続可能な社会への転換を図る必要があります。私たち一人ひとりがプラスチック使用を見直し、この地球規模の課題解決に貢献する意識が今、求められています。
参考資料
- Yahoo!ニュース (新潮社)
- 東京農工大学
- 東京理科大学