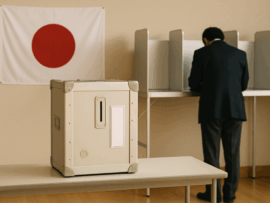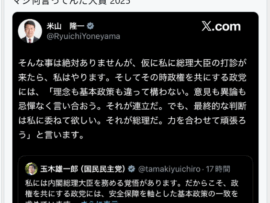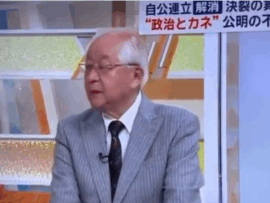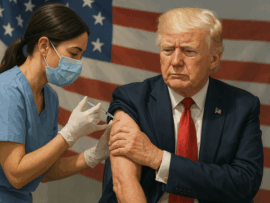「福島第一原発事故以降、原発反対の声はあげやすくなりましたが、事故発生から14年5カ月が過ぎた今は、また反対意見が言いにくい雰囲気に戻っていると感じます」。日本のエネルギー政策、特に原子力発電の問題に30年近く向き合ってきたフリージャーナリストの青木美希氏は、現在の日本社会の状況に警鐘を鳴らしています。未曽有の福島第一原発爆発事故の記憶が薄れゆく中で、「原発は安全でクリーン、そして安価だ」という誤った認識が再び広がりつつある現状は、日本の未来のエネルギー選択に大きな影響を与える可能性があります。
福島事故から14年:日本のエネルギー政策の変遷と「原発回帰」
2011年の東日本大震災と福島第一原発事故という未曽有の事態を受け、当時の日本の民主党政権は「原発ゼロ」政策を推進しました。しかし、2012年末に政権を奪還した自民党の安倍晋三政権は、既存の原発再稼働へと方針を転換。そして2022年のウクライナ戦争勃発によるエネルギー危機などを機に、日本政府は本格的な原発回帰へと舵を切っています。
この政策転換は具体的な数字にも表れています。福島第一原発事故後に確立した「原発稼働期限40年」原則は、2023年6月に事実上放棄され、60年を超える運用が容認される運びとなりました。さらに今年2月には新たな「エネルギー基本計画」が閣議決定され、原発が発電量全体に占める割合を2022年時点の5.5%から、2040年度には20%ほどにまで拡大する目標が掲げられました。これは、昨年の時点で原発の割合が32.5%にのぼる韓国と比較しても、今後の日本の原子力依存度の上昇を示唆しています。
 日本のフリージャーナリスト青木美希氏、福島第一原発事故の現場を取材
日本のフリージャーナリスト青木美希氏、福島第一原発事故の現場を取材
「原発は安全」という誤った情報と報道の現状
青木氏は、このような政策転換の背景には、SNSを中心に「原発は安全だ」という主張が活発に広まっている現状があると指摘します。「原発は安全、クリーン、安い、という誤った原発神話が再び広がっているのを実感します」と青木氏。
その影響は報道現場にも及んでいます。青木氏によると、「福島事故の汚染の現状を伝えようとしてもデスクに阻まれる事例が出ています。健康被害を伝えようとした記者も企画をつぶされました」。また、政治の世界でも「自民党地方議員のなかにも『脱原発と思っているが党の方針と違うから言えない』という人もいます」と、本音と建前が乖離している現状を明らかにしました。経済界からの圧力も存在し、青木氏は「日本経済団体連合会の幹部に『日本は原発がないから衰退したんだ』と批判的に言われました」と語り、多様な方面からの「原発推進」の声が社会を覆いつつあると警鐘を鳴らしています。
福島取材とジャーナリストの使命:青木美希氏の活動
青木美希氏が原子力問題に深く関わるのは、父親が原子力の研究者だったという背景も影響しています。父親の教え子たちが被ばくを心配する姿を間近で見てきた経験が、原発の「素顔」に迫ろうとする彼女の原点となりました。北海タイムス、北海道新聞社、全国紙などを経て、現在はフリーランスとして活動する青木氏は、記者歴約30年のほとんどを原発取材に捧げてきました。
特に福島第一原発事故は、青木氏のジャーナリストとしての使命感を一層強固なものにしました。「福島第一原発事故で50万人超の方々が避難する姿を見て、報道が足りなかった、と反省をしました」。上司から「いつまで避難者の取材をやっているのか」と言われながらも取材を続け、最終的には2020年に記者職を外されることに。しかし、彼女はそこで諦めることなく、休暇の時間と個人の資金を使い、フリーランスとして取材を続けています。今年4月には韓国語版が出版された『なぜ日本は原発を止められないのか?』の著者でもある彼女の活動は、その強い信念に支えられています。
 2020年11月、福島第一原発を視察する青木美希氏
2020年11月、福島第一原発を視察する青木美希氏
日本のエネルギー転換への課題:既得権益と地域格差
韓国と同様、日本も首都圏に多くの人口が集中していますが、首都圏などの大都市のエネルギー自給率は非常に低いのが現状です。気候危機時代におけるエネルギー転換は、日本にとって極めて難しい課題の一つであり、青木氏は脱原発がうまくいかない原因として、強力な既得権益勢力の存在を指摘します。
「既存の原発を動かすのはやむを得ない、新規は認めない、という政治家もいます。一方で、両方とも賛成の政治家もいます。被害の実態をどれほど知っているかによるのだと思います」と青木氏は語り、「原子力で潤う一部の人たちが自らの利益を守るために進めています。日本では『既得権益』と呼んでいます」と批判しました。
さらに、原発が建設、運用されても地域住民には本質的な利益が回らない構造も問題視されています。「日本は交付金や匿名寄付という形で自治体が潤ったり、漁業者には補償が出たりします。ただ、一時は潤ってもその後は衰退に向かい、また新たな原発を求めるという構造になっています」と指摘し、これが地域社会を原発への依存から抜け出せなくしていると強調しました。
持続可能な電力システムへの提言と日韓協力
青木氏は、日本がこれまでの原発中心のエネルギー政策から脱却し、再生可能エネルギー、蓄電池、送電網整備など、新たな電力システムの構築が必要だと主張します。「地産地消、営農型ソーラー、小水力、洋上風力。日本でも再エネを進めようと動いている人たちはいます」と述べ、地域に根ざした多様な再生可能エネルギーの可能性に言及しました。
そして、類似した課題を抱える日本と韓国が、エネルギー転換に関する情報交換をしていくことが重要であると語っています。両国が協力し、持続可能で安全なエネルギー未来を共に模索していく姿勢が、今後の重要な鍵となるでしょう。
結論
ジャーナリスト青木美希氏の30年にわたる原発取材は、福島の教訓が忘れ去られ、「原発神話」が再び力を持ち始める日本の現状を浮き彫りにしています。エネルギー危機を背景とした原発回帰の動き、既得権益の存在、そして報道現場での課題は、日本のエネルギー政策が単なる技術的な選択に留まらない、複雑な社会・政治的構造を抱えていることを示唆しています。
しかし、青木氏の活動や、再生可能エネルギー推進に動く人々の存在は、持続可能な未来への希望も示しています。福島事故を経験した日本が、その教訓を真に活かし、透明性のある議論と市民参加を通じて、国民が納得できるエネルギーの選択をしていくことが今、強く求められています。
参考文献: