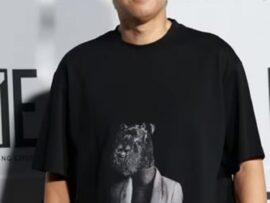生成AI(人工知能)の急速な進化が、世界経済に大きな影響を与え始めています。特にアメリカでは、この新たな技術が「就職氷河期」の到来を加速させ、大卒以上の若者層に深刻な失業問題を引き起こしていると日米の複数メディアが報じています。ニューヨーク連邦準備銀行が今年4月に発表した衝撃的な報告書によると、22歳から27歳までの大卒者の失業率は5.8%に達し、労働者全体の失業率4.0%を1.8%も上回る結果となりました。この差は過去最悪を記録しており、若者のキャリア形成における新たな課題が浮上しています。
AIが変える雇用市場:IT専攻者の逆境と哲学専攻者の意外な強み
この失業率の統計で特に注目すべきは、AI技術と密接に関わる専門分野の若者たちの厳しい現状です。報告書によれば、「コンピューターサイエンス」を専攻した若者の失業率は6.1%、「コンピューター工学」の若者は7.5%と、いずれも大卒平均の5.8%を上回る結果となりました。一方で、一般的に就職に不利なイメージがある「哲学」を専攻した若者の失業率は3.2%と、コンピューター関連分野の専門家よりも低いという意外なデータが示されています。
この逆転現象の背景には、生成AIの進化があります。これまでIT企業が好景気を牽引し、名門大学のコンピューター専攻者が新卒で年収1000万円以上を得ることも珍しくありませんでした。しかし、新入社員が担当していた初歩的なプログラミング、データリサーチ、報告書作成といった基礎的な業務の多くが、今や生成AIによって効率的に代替可能になったのです。これにより、IT企業は新卒採用を控える傾向にあり、コンピューター関連分野を学んだ若者たちが就職難に直面しています。
 新卒採用の面接で不採用通知を受け取り落胆する若者のイメージ。AIによる就職難が背景にある現状を象徴。
新卒採用の面接で不採用通知を受け取り落胆する若者のイメージ。AIによる就職難が背景にある現状を象徴。
加速する「AIリストラ」:大手企業から新卒キャリアの危機まで
生成AIの影響は、若者の新規採用市場に留まりません。世界的経済誌フォーブスの日本語電子版が7月15日に配信した「加速する『AIによるリストラ』、米テック・メディア大手が人員削減に踏み切る」という記事は、この深刻なトレンドを明確に示しています。この記事は、グーグル、マイクロソフト、メタ、インテル、IBMといったIT業界の巨人だけでなく、金融大手JPモルガン・チェースのような異業種においても、生成AI導入による大規模な人員削減が進んでいると報じました。
ITジャーナリストの井上トシユキ氏は、この状況について「日本で報じられている以上に、アメリカでは大騒ぎになっているようです」と警鐘を鳴らしています。理系の超難関大学として知られるカリフォルニア工科大学の卒業生でさえ、就職活動で100社にエントリーしても面接にすら呼ばれず、全て書類選考で不採用となるケースが報じられているとのことです。生成AIが、入社1、2年目の若手社員が担う初歩的なプログラミング、リサーチ、報告書作成といった業務を代替していることは事実であり、井上氏は「新入社員としてキャリアをスタートさせる最初の入口が閉ざされつつある」現状を特に問題視しています。これは、ごく一部の天才的な若者でなければ職を得られないという風潮を生み出し、長期的なキャリア形成に大きな影を落としています。
AIによって代替される可能性のある職業が示唆されており、日本の読者にも関連が深いことを示唆する画像。
日本への影響とAIの「過大評価」論
アメリカで起きているこの「AI就職氷河期」は、遠い国の出来事ではありません。同様の状況が日本でもあっという間に到来する可能性は高く、多くの日本人にとって不安材料となるでしょう。しかし、井上氏は「生成AIが過大評価されているのも事実だと思います」と指摘し、AIの影響を冷静に評価する必要性も示唆しています。
生成AIの発展は雇用市場に前例のない変化をもたらしており、特に若者のキャリアパスに大きな影響を与えています。基礎的な業務がAIに代替される一方で、人間ならではの創造性、批判的思考、共感といったスキルがこれまで以上に重要になる時代が来ています。企業側も、AIを単なるコスト削減ツールとしてだけでなく、新たな価値創造のパートナーとして活用し、人間とAIが共存する未来の働き方を模索する必要があるでしょう。
参考文献
- ニューヨーク連邦準備銀行 報告書(2024年4月発表)
- フォーブス日本語電子版「加速する『AIによるリストラ』、米テック・メディア大手が人員削減に踏み切る」(2024年7月15日配信)
- 井上トシユキ氏(ITジャーナリスト)のコメント
- Yahoo!ニュース記事(2025年9月5日配信)