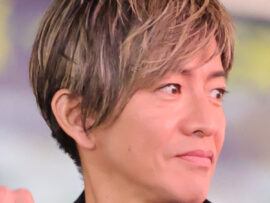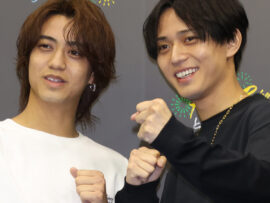1967年10月20日、吉田茂氏はこの世を去りました。享年89。外務大臣、そして首相として戦後日本の礎を築き、1951年9月8日には首席全権としてサンフランシスコ平和条約および日米安全保障条約に署名した、日本を代表する政治家です。その偉大な功績は、戦後初の「大勲位菊花章頸飾」受章、ノーベル平和賞に3度推薦、そして総理経験者としては初の国葬など、枚挙にいとまがありません。
 1957年、大磯の邸宅で葉巻を手にカメラを見つめる吉田茂氏。戦後日本の首相の貴重な素顔。
1957年、大磯の邸宅で葉巻を手にカメラを見つめる吉田茂氏。戦後日本の首相の貴重な素顔。
生前は、その一挙手一投足が世間の注目の的となり、時には厳しい批判にもさらされた吉田氏。その死は、遺族たちにとっても大きな転機となりました。当時の「週刊新潮」は、この歴史的な出来事を次のように報じています。
〈「父・吉田茂」の死を境に、遺族たちはよりいっそうの名声と世間の注視を受ける立場に立った。遺族の立場からいえば、いや応なく、そういう立場に追い込まれたといえそうである〉(1967年11月4日号「吉田四姉弟の人生態度 名声と注視の中での生き方」より)
強い個性で知られた吉田氏は、雪子夫人(1941年死去)との間に5人の子どもをもうけましたが、次女は若くして亡くなりました。常に世間の注目を浴びる父親の元で、残された子どもたちは一体どのように育ち、その後どのような人生を歩んだのでしょうか。「週刊新潮」の当時の記事から、吉田家の育児方針や雪子夫人の人柄に迫ります。(以下、引用部分はすべて「週刊新潮」1967年11月4日号からの抜粋を現代の表記に修正したものです)
「名声と注視」の中で生きる吉田家の四姉弟
吉田茂氏の死後、彼の家族は否応なく、その偉大な名声と世間の注視の的となりました。父親の強烈な存在感の下で育った子どもたちは、それぞれ異なる道を歩んでいます。特に、これまでほとんど世間に知られていなかった長女・桜子さんと次男・正男氏の生き方は、吉田家の知られざる側面を浮き彫りにします。
長女の桜子さんは戦前に外務省の男性と結婚し、夫の死後は都内のカトリック系病院で奉仕活動に身を捧げました。一方、学者肌であったという次男の正男氏(2005年死去)は、複数の言語を操る優秀なエンジニアとして、GHQや国連関連の要職を務め、後には大学教授としても活躍しました。彼ら兄弟の生き様は、公的な場での華々しさとは異なる、静かで実直な吉田家の姿を映し出しています。
次男・正男氏の「父は総理」秘話と雪子夫人の影響
次男・正男氏に関する印象的なエピソードは、彼の控えめな人柄と育ちの良さを物語っています。ある外務省の高官は、GHQ時代に正男氏と連日顔を合わせていたにもかかわらず、彼の父親が吉田茂氏であるとは全く知らなかったと証言しています。
〈「ところが彼は、父親のことを一言もいわない。こちらは外務省の後輩として、吉田さんにも可愛がられていたのだが、その私も『吉田』という名前を彼の親父さんに結びつけたことはなかった。それが、つき合いはじめて1年してからだったと思う。なにかの話のついでに彼が『父は総理だもんだから……』といったんです」〉
この高官は、正男氏の告白に「からかわれた」と思うほどの衝撃を受けたといいます。しかし、「週刊新潮」はこれを父・吉田茂氏のような悪戯とは異なると指摘しています。
〈事実、人をからかうのが好きな父親の吉田氏なら、このぐらいのイタズラはやりかねない。だが、正男氏は、どちらかといえば母親の雪子夫人の生真面目な性格を受け継いでいる人だ。もちろん、イタズラでもなんでもなかった〉
このエピソードは、正男氏が父親の権威に頼ることなく、自身の能力と努力で道を切り開いてきたことを示唆しています。また、彼の誠実な性格が、早くに亡くなった雪子夫人の影響を強く受けていたことがうかがえます。吉田家の子どもたちは、それぞれの方法で偉大な父親の影と向き合い、自らの人生を切り拓いていったのです。
吉田茂という巨星の光は、その家族の人生にも深く影響を及ぼしました。彼の死後、世間の注目を一身に集めた遺族たちは、それぞれが独自の人生態度を貫き、父親の偉大さとは異なる形で社会に貢献しました。これは、名宰相の家族として生きることの重みと、個々の人間としての尊厳を両立させた、示唆に富む物語と言えるでしょう。
参考資料
- 週刊新潮 1967年11月4日号 「吉田四姉弟の人生態度 名声と注視の中での生き方」