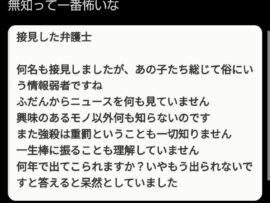[ad_1]
新潟県と愛知県のラジオ局が6月末、相次いで閉局した。地域の文化を担う存在として親しまれてきたが、広告収入の減少で経営状態が悪化し、改善が見込めなかった。これまで在宅時間のお供や、災害時の情報源として、ラジオは大きな役割を果たしてきたが、聴取者の高齢化やインターネットの普及など、業界を取り巻く環境は大きく変わってきている。専門家は「ラジオというメディアの価値が今一度、問われている」と指摘する。 (文化部 三宅令)
大口スポンサーの撤退
「閉局を告げられたのは、発表の1週間前。突然のことで、びっくりして笑うしかなかった」
6月末に閉局した「新潟県民エフエム放送(FM PORT)」で、開局当初からパーソナリティーを務めてきた遠藤麻理さん(47)は、その日のことを振り返る。
同局は県内全域をエリアとする民間FM局。ほぼ全ての番組を自社制作し、地域に密着した放送局として親しまれていた。
「今年の12月で開局20周年だった。小さいときに母親と一緒に番組を聞いていた子が就職したことを教えてくれたりとか…。リスナーとの思い出は尽きませんね」と話す。
閉局は広告収入の減少による経営悪化が主な原因だ。大口スポンサーから今後の広告出稿を取りやめる意向が示されたことが、決定打になった。新型コロナウイルス禍で在宅時間が増え、これまで縁遠かった若年層も、ラジオを聞いてくれるようになったと感じていた矢先の出来事だった。
「ラジオの良いところは1対1の距離感。こういう時こそ、リスナーのそばにいたかった」
「娯楽の王様」競争の時代
名古屋市のFMラジオ局「Radio NEO(レディオネオ)」も6月30日、経営悪化を理由に閉局した。
「初めてラジオに自分の曲が流れたときは感動した。『自分たちも売れたなあ』って思ったものです」
デビューから半世紀の兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝さん(75)と、進さん(72)はラジオが覇権メディアだった時代を知っている。
ラジオは戦前から昭和の庶民の娯楽だった。テレビの台頭でその地位を追われたが、深夜放送や高音質のFM放送などがブームとなり、独自の魅力を確立。平成7年の阪神・淡路大震災では、災害時の頼れる存在として注目された。
一方でリスナーの高齢化は進んだ。NHK放送文化研究所によると、1日のなかでラジオを聴く人が最も多い年齢層は、昭和50年は16~19歳だった。平成7年は50代が最も多く、27年は70歳以上となっている。
また、22年にインターネットでラジオ番組が聞ける「radiko(ラジコ)」がサービスを開始。放送域内のラジオはもちろんだが、全国のラジオも有料で聞けるようになったことで、以前よりも各局のコンテンツ力が試されるようになった。それまで、電波が届くその地域内での競争だったものが、ネット上では全国横並びでの競争となるからだ。
首都圏のキー局に比べて資金力に乏しい地方局にとっては、一層厳しい経営環境となっている。
問い直される役割
総務省の統計によれば、各ラジオ局の放送地域を限定するという放送法の制度もあり、全国に約100局の民間ラジオ局(放送エリアが狭いコミュニティー放送局を除く)が存在する。メディア文化評論家の碓井広義氏はこの100局について「今となっては多過ぎる」と指摘する。「ネットメディアの台頭もあり、(言論の多様性の確保を目的とした)マスメディア集中排除原則は緩和されつつある。今後、ラジオ局の統廃合が進むだろう」と話す。
相次いだ閉局は変化の予兆に過ぎない。「今後、広告収入だけのビジネスモデルでは限界がくる」として、「新たな収入源の模索と並んで、ラジオならではの魅力や果たすべき役割について、もう一度考えていく必要がある」と話した。
ネットの台頭による地方局の苦境は、テレビが置かれた状況も相似形の可能性が高い。長く覇者だった電波メディアの変化は始まったばかりだ。
[ad_2]
Source link