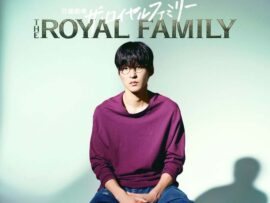甲府市中心部を流れる濁川の上に立つ民家について、山梨県は河川法に基づく強制撤去に着手した。倒壊を恐れていた人々からは「ようやく撤去が始まって安心だ」との声が上がる。一方、所有者は不明で、民家を撤去する費用は税金で賄われるため、「本来は持ち主が負担すべきだ」との意見も聞かれる。(高村真登)
【写真】床が崩れた民家の下を流れる濁川
老朽化におびえ

撤去が始まった民家。地下には濁川が流れる(2日、甲府市で)
「風が強い日は民家が倒壊するのでは、と怖かった。雨の日は下水のような臭いが充満していた」。民家の隣にある人材派遣会社「アンサーノックス」の渡辺郁(かおり)社長(51)は語る。
今回、撤去が始まった11棟はJR甲府駅前の平和通り沿いに長屋のように連なり、幅4・4メートルの川の暗渠(あんきょ)(地下水路)の上に立っている。傷みが激しく、一部傾いているものもある。昨年5月には1棟の床が抜け、住人の女性が救助されるトラブルもあった。
同社は民家の倒壊を懸念して、隣接する位置にあったガスボンベを自費で移設したという。渡辺社長は「従業員や近隣住民の安全のためにも早急に撤去してもらいたいと思っていた」と話す。
異例のケース
県中北建設事務所によると、これらの民家は戦後、甲府駅周辺の区画整理に伴い、立ち退きを求められた家や店舗の一部が移転したものという。建築された1958年頃は、「河川区域の土地を占有するには許可を受けなければならない」とする「河川法」の適用を受ける前だった。県も「倒壊の危険性が高い」として撤去を検討してきたが、河川法適用前の建築物は違法ではなく、住人もいたため手を打てずにいた。
ところが、昨年の床が抜けるトラブルの後、救助された女性も民家を離れ、全て空き家になったことから、県は強制撤去の検討に入った。国土交通省に対し、所有者不明の工作物を強制撤去する「簡易代執行」の適用が可能か問い合わせた。国交省は「不法係留の船などに適用される場合が多く、民家の強制撤去はこれまでにないケースだ」としたが、法律上は問題ないとの見解を示した。県は2日に工事に着手。今月末頃までに解体を終える予定だ。