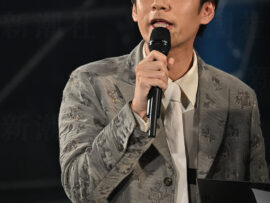近年、ネット配信サービス開始に伴い、受信料問題がますます注目されるようになったNHK。その裏では、なんと約9000億円もの金融資産が「蓄財」されているという驚きの事実が! これだけの資産を抱えながら、果たしてNHKは公共放送としての役割を十分に果たせているのでしょうか? 本記事では、専門家の意見も交えながら、NHKの現状と課題に迫ります。
公共放送としての在り方とは?
立教大学社会学部の砂川浩慶教授(メディア論)は、NHKのバラエティ番組が近年、民放と変わらない内容になっている点を指摘し、「民放と同じような番組を作る意味はありません」と断言します。
砂川教授は、NHKが本来取り組むべきなのは、「障害者の方や少子高齢化の当事者の人たちに目線を合わせるなど、経済原則には合わないけれど重要な番組を多く作るべき」だと主張します。
軽視される災害報道、問われる公共放送としての責任
一方で、砂川教授は、2026年度からAMラジオを1波減らすというNHKの方針にも疑問を呈します。
「今回の能登など、激甚災害の発生時には電源が失われ、ラジオが唯一の情報源となることも少なくない。そうした非常時に必要とされる放送こそ、NHKが担うべきものではないでしょうか」(砂川教授)
実際、最近のNHKは過去の映像の再放送を多用したり、関東地方の大雨の最中にラジオで娯楽番組を放送したりするなど、視聴者が本当に求める情報提供を軽視しているように思える事例が目立ちます。
 NHK放送センター
NHK放送センター
コストカットの影響か? 報道の弱体化と無駄な支出
こうした報道の弱体化は、全体的なコストカットの影響だと指摘する関係者もいます。 一方で、別の関係者は、NHK内部では高額な人事管理システムを導入したものの、組織に合わず、わずか1年で別のシステムに乗り換えるなど、無駄な支出も目立つと明かします。
NHKの真価が問われている
ハイビジョンの開発など、技術革新に貢献してきたNHK。しかし、その一方で、巨額の資産を保有しながら、公共放送としての役割を軽視しているとの批判も免れません。
視聴者にとって本当に必要な情報を発信し、災害時にも頼りになる存在であり続けるために、NHKにはその真価が問われています。