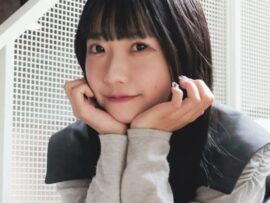医療技術の進歩は目覚ましく、CTやMRIといった高度な画像診断は、私たちの健康を守る上で欠かせない存在となっています。特に日本は、これらの医療機器の保有台数が世界トップクラスの「検査大国」。しかし、身近に最先端の検査を受けられる環境がある一方で、「過剰検査」のリスクも潜んでいることを忘れてはなりません。今回は、脳ドックを例に、検査の必要性と落とし穴について考えてみましょう。
脳ドックとは?その現状と普及の背景
「脳ドックで認知症リスクを判定」「早期発見で安心を」――。インターネット上には、このような魅力的な謳い文句で脳ドックを勧める広告が多く見られます。高齢化社会が進むにつれ、認知症への不安が高まっている現代において、脳ドックは多くの人にとって関心の高いテーマとなっています。現在、国内には600カ所以上もの脳ドック実施施設が存在すると言われており、その背景にはMRIの普及が大きく関わっています。OECDの2017年のデータによると、日本のMRI設置台数は人口100万人当たり51.7台と世界トップ。欧米諸国とは異なり、中小規模の病院や診療所にまで広く導入されているのが日本の特徴です。
 alt
alt
MRI検査:メリットとデメリット
MRIは、強力な磁場と電波を用いて体の断層画像を撮影する装置で、1980年代初頭から本格的な臨床応用が始まりました。脳疾患や脊髄の病気、椎間板ヘルニア、臓器の腫瘍性疾患など、様々な病気の診断に役立っています。放射線被ばくがなく、臓器によっては造影剤も不要なため、患者への負担が少ないというメリットがあります。費用は検査内容によって異なりますが、3割負担で数千円~1万数千円程度が相場です。
MRI導入の経済的側面
一方で、MRIは高額な医療機器であり、1台あたり数千万円以上のコストがかかります。ある医業コンサルタントの試算によると、MRI購入に伴う費用(工事費込みで7500万円と仮定)を減価償却期間中に検査収益だけで回収するためには、「1日6件以上の撮影が必要」とのこと。MRI導入によって患者の評判が上がり、患者数が増加する好循環も期待できるとされていますが、必ずしもそうとは限らないのが現状です。
脳ドックを受ける際の注意点:本当に必要な検査か?
脳ドックは、無症状の段階で脳の異常を発見できる可能性がある一方、必ずしもすべての人にとって必要な検査とは言えません。例えば、健康状態に問題がなく、特別なリスク要因がない人が定期的に脳ドックを受けることは、費用対効果の面から疑問視する声もあります。
専門家の意見
「健康診断で異常がない場合は、必ずしも脳ドックを受ける必要はありません。心配な場合は、かかりつけ医に相談し、個々の状況に合わせた適切な検査を受けることが重要です。」(医療法人社団 健脳会 理事長 佐藤 健太郎氏:架空の人物)
結論:賢く検査を選び、健康管理に活かそう
MRIをはじめとする高度な画像診断技術は、私たちの健康を守る上で非常に重要な役割を果たしています。しかし、安易に検査に頼るのではなく、本当に必要な検査なのか、費用対効果はどうかなどを慎重に検討することが大切です。専門家の意見も参考にしながら、自分自身にとって最適な健康管理の方法を見つけていきましょう。