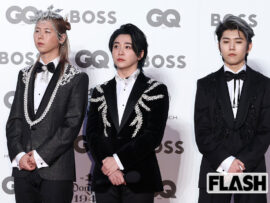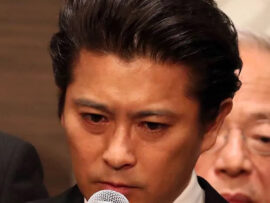日本の伝統行事、節分。豆まきや恵方巻きで馴染み深いイベントですが、毎年日付が変わることに疑問を持ったことはありませんか? 今年は2月2日でしたが、なぜ毎年2月3日ではないのでしょうか? 今回は、節分の日付が変わる理由を分かりやすく解説します。お子様にも理解しやすいように、専門家の意見も交えながら、豆まきの由来や恵方巻きの楽しみ方についても触れていきます。
節分とは? なぜ日付が変わるの?
そもそも節分とは、季節の変わり目を意味する言葉です。本来は立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれ前日を指していましたが、現在では立春の前日が「節分」として定着しています。立春は暦の上で春の始まりを告げる大切な日。 その立春の前日である節分は、冬から春への移り変わり、つまり邪気を祓い清める大切な日と考えられています。
 京都市の廬山寺に現れた鬼たち
京都市の廬山寺に現れた鬼たち
国立天文台の暦計算室長、暦のプロフェッショナルである小野寺氏(仮名)によると、地球が太陽の周りを一周する周期は、厳密に言うと365日ではなく、約365.2422日。この僅かな差が、節分の日付の変動に繋がっています。4年に一度うるう年を設けて調整していますが、それでも完全に一致するわけではなく、わずかなずれが生じてしまうのです。特に、2000年のような400で割り切れる年の前後は、このずれの影響を受けやすく、節分の日付が変動しやすくなるとのこと。
豆まきで邪気払い! 恵方巻きで福を呼び込もう!
節分といえば、欠かせないのが豆まき。炒った大豆を「鬼は外、福は内」と唱えながら撒き、邪気を祓い、福を呼び込みます。 小野寺氏によると、豆まきの起源は中国の追儺(ついな)の儀式にあると言われています。鬼を模した厄災を追い払うことで、無病息災を祈願するという意味が込められています。

近年では、恵方巻きを食べる習慣も広まっています。その年の恵方を向いて、願い事をしながら無言で食べると願いが叶うと言われています。 恵方巻きは、七福神にちなんで七種類の具材を入れるのが一般的。 家族みんなで楽しめるイベントとして、節分に恵方巻きを食べる習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。
節分は家族で楽しむ日本の伝統行事
節分は、ただ単に豆まきをする日ではありません。古来より受け継がれてきた伝統行事を通して、家族の絆を深め、新しい季節への希望を繋ぐ大切な日です。 暦の仕組みを理解することで、節分への関心もより一層深まるのではないでしょうか。 今年の節分は終わりましたが、来年の節分がいつになるのか、ぜひ家族で話してみてくださいね。