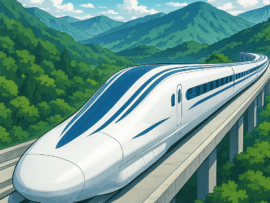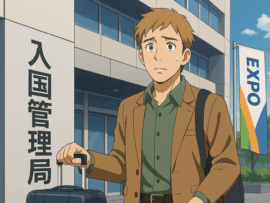現代社会において、子どもたちの「読解力」低下が深刻な問題となっています。全国学力テストの結果からも、中学生の国語の「読む力」の低下が顕著に表れています。本記事では、読解力低下の原因やその影響、そして私たちにできる対策について探っていきます。
読解力低下の現状
近年、子どもたちの読解力低下が様々な場面で指摘されています。2024年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)では、中学生の国語の平均正答率が前年度より大幅に低下しました。SNSでの短文コミュニケーションや動画視聴の増加など、活字離れが背景にあるとされています。
 alt=真剣な表情でテストに取り組む中学生
alt=真剣な表情でテストに取り組む中学生
読解力低下の要因:コロナ禍とタイパ主義
「ただよび」校長で現代文講師の宗慶二氏によると、現代文の成績は二極化が進み、特に中間層の学力低下が目立つとのこと。読解力低下の要因として、コロナ禍による対面交流の減少を挙げています。オンライン授業の普及により、子どもたちは他者の反応を意識する機会が減り、社会性や共感力の低下につながっている可能性があります。
また、受験勉強における「タイパ」(タイムパフォーマンス)重視の風潮も影響していると考えられます。効率的に点数を取るためのテクニック学習に偏り、文章を深く理解する姿勢がおろそかになっているかもしれません。
読解力とは何か:共感力と多角的思考力の重要性
宗慶二氏は、読解力とは単に文字を追うだけでなく、相手の気持ちを理解する共感力、場の空気を読む力などを含めた総合的な能力だと指摘します。相手の表情や言葉のニュアンスから真意を読み取る力も、広い意味での読解力と言えるでしょう。
 alt=教科書を読む生徒
alt=教科書を読む生徒
現代の子どもたちは、明確な根拠に基づいた解答を求める傾向が強いそうです。「桜咲く」という表現から、合格を連想するような、行間を読む力や想像力が不足している可能性も懸念されています。
読解力向上のための対策
読解力を育むためには、幼少期からの読書習慣の確立が重要です。様々なジャンルの本に触れることで、語彙力や表現力を高め、多角的な視点を持つことができます。また、家族や友人との会話、社会経験を通して、共感力やコミュニケーション能力を養うことも大切です。
未来への提言:読解力向上で豊かな社会を
読解力は、学業だけでなく、社会生活を送る上でも必要不可欠な能力です。子どもたちの読解力向上に向け、家庭、学校、社会全体で取り組む必要があります。読書の楽しさを伝える、対話を通して共感力を育むなど、様々なアプローチで未来を担う子どもたちの成長をサポートしていきましょう。