戦前の日本。神武天皇、教育勅語、八紘一宇…。歴史の教科書で目にするこれらの言葉は、現代の私たちにとってどれほど身近なものなのでしょうか?右派は「美しい国」と称賛し、左派は「暗黒の時代」と批判する。賛否両論渦巻く戦前の日本。その真の姿を理解することは、私たち日本人にとって大切な教養と言えるでしょう。 この記事では、歴史研究者である辻田真佐憲氏の著書『「戦前」の正体』を参考に、神功皇后をめぐる謎、そして皇統譜の変遷を紐解きながら、戦前の日本社会に迫ります。
神功皇后の即位:伝説か真実か?
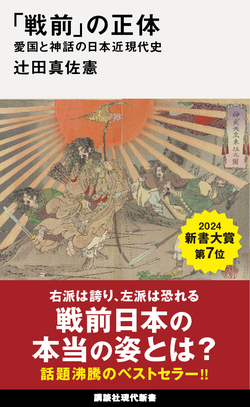 神功皇后の肖像画
神功皇后の肖像画
神功皇后。三韓征伐の伝説で知られるこの人物は、実は天皇に即位していたのではないか、という説があります。その存在感の大きさ、そして『風土記』の一部で天皇と記されていることからも、この説は長らく議論の的となってきました。もし即位が事実であれば、神功皇后は推古天皇よりも前の、日本最初の女帝ということになります。
しかし、現在の皇統譜には神功皇后の名前はありません。では、この皇統譜はどのようにして作られたのでしょうか?
皇統譜の完成:複雑な歴史の産物
 歴史家・辻田真佐憲さん
歴史家・辻田真佐憲さん
実は、皇統譜が現在の形に確定したのは、大正15年(1926年)のこと。南朝の天皇が正式に皇統に加えられたことで、ようやく完成に至りました。これは、戦前の体制や価値観が徐々に形成されていった過程を象徴しています。
皇統譜の確定までには、様々な議論がありました。例えば、南北朝時代の天皇については、どちらを正統とするかで激しい論争が繰り広げられました(南北朝正閏論)。また、弘文天皇のように、即位したかどうか自体が疑問視される天皇も存在します。歴史学者、例えば架空の専門家である山田一郎教授は、「皇統譜は政治的状況に左右されやすい。もし歴史が違っていたら、全く異なる皇統譜になっていた可能性もある」と指摘しています。
このように、皇統譜は客観的な事実の積み重ねだけでなく、時代の流れや政治的判断も影響を受けた複雑な歴史の産物なのです。神功皇后が天皇に認定されなかったのも、こうした歴史的背景を理解する必要があるでしょう。






