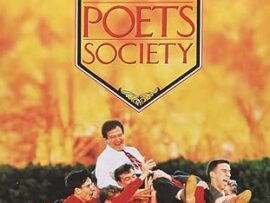永久凍土の融解が、新たな感染症パンデミックの引き金となる可能性が懸念されています。ダイヤモンド・プリンセス号のコロナウイルス騒動から5年、地球温暖化の影響で永久凍土に閉じ込められていた古代のウイルスや細菌が復活し、人類に脅威を与えるリスクが現実味を帯びてきました。遠い国の話と思われがちな永久凍土ですが、実は日本にも存在します。今回は、土壌学者の藤井一至氏(仮名)や国立環境研究所の横畠徳太氏の知見を交えながら、永久凍土融解の現状と感染リスク、そして私たちの暮らしへの影響について探っていきます。
永久凍土に潜む未知のウイルス:パンデミックの可能性は?
永久凍土とは、2年以上連続して地下の温度が0℃以下になっている土壌のこと。氷河期に形成されたものも多く、数万年前の動植物の遺骸や病原菌、ウイルスなどが凍結保存されています。近年、これらの病原体が現代に蘇る可能性が注目を集めています。
2022年には、フランスの研究チームがシベリアの永久凍土から7種類の古代ウイルスを発見。これらのウイルスは、過去に発見されたパンドラウイルスやモリウイルスと同様に、細胞に感染する能力を持つと報告されています。また、2016年にはシベリアで永久凍土中のトナカイの死骸から炭疽菌が発生し、2000頭以上のトナカイと70人以上の住民が感染、死者も出る事態となりました。
 alt:シベリアの永久凍土。広大な大地に広がる凍土は、温暖化の影響で融解が進んでいる。
alt:シベリアの永久凍土。広大な大地に広がる凍土は、温暖化の影響で融解が進んでいる。
こうした事例から、永久凍土由来のウイルスによるパンデミックの危険性が叫ばれていますが、その信憑性はどうなのでしょうか。土壌学の専門家である藤井一至氏(仮名)は、「感染リスクはゼロとは言えません。しかし、土壌中のウイルスの特性や永久凍土地帯の環境を考えると、大規模な感染拡大は起こりにくいでしょう」と指摘します。
足元の土にもウイルスは存在する:永久凍土だけが危険ではない
永久凍土だけでなく、私たちの足元の土壌にも無数の未知のウイルスが存在しています。藤井氏(仮名)によると、「土壌は微生物の宝庫であり、ウイルスもその一部です。しかし、ほとんどのウイルスは人間に無害であり、病原性を持つものはごくわずかです。永久凍土の融解によって未知のウイルスが放出される可能性はありますが、過度に恐れる必要はありません。むしろ、土壌生態系のバランスを保つことが重要です」。
私たちにできること:温暖化対策と適切な土壌管理
永久凍土の融解は、地球温暖化の進行を示す重要なサインです。温暖化対策を進めることは、感染症リスクの軽減だけでなく、地球環境の保全にも繋がります。また、土壌を適切に管理することも重要です。過剰な開発や農薬の使用は、土壌生態系を破壊し、未知のウイルスが活性化するリスクを高める可能性があります。
永久凍土融解の影響:暮らしと地球環境へのリスク
永久凍土の融解は、感染症リスク以外にも様々な影響を及ぼします。横畠氏によると、「永久凍土には大量の有機炭素が蓄積されており、融解によってメタンや二酸化炭素などの温室効果ガスが大気中に放出されます。これは地球温暖化を加速させ、更なる永久凍土の融解を引き起こす悪循環に繋がります」。また、永久凍土の融解は地盤沈下を引き起こし、インフラの崩壊や生態系の変化にも繋がります。
私たちの暮らしを守るためにも、永久凍土融解の現状を正しく理解し、地球温暖化対策と適切な土壌管理に取り組むことが重要です。