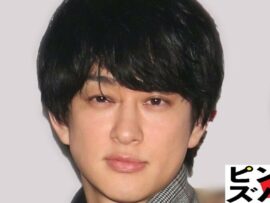大阪市北区にある滝川小学校。目の前のブロックに住んでいるのに、指定の通学先は500メートル離れた堀川小学校。一見いびつなこの学区設定には、150年以上もの歴史が深く関わっているのです。この記事では、滝川小学校と堀川小学校の学区の謎に迫り、地域と学校が築き上げてきた深い絆について探っていきます。
明治時代からの歴史:地域が支えた小学校教育
滝川小学校の起源は明治5年に設立された「北大組第4区小」、堀川小学校は翌年に設立された「北大組第7区小」です。当時は町丁単位で学区が設定されており、両校とも地域に囲まれた場所に校舎がありました。しかし、明治44年に滝川小学校が堀川小学校の学区との境界付近に移転。これが現在の学区設定の礎となったのです。
 滝川小学校の校舎
滝川小学校の校舎
明治初期、小学校は行政ではなく地域住民が資金を出し合い、運営していました。教師の給与も地域負担だったため、地域の経済力が教育内容に直結していた時代でした。北区役所の担当者は、「小学校と地域の結びつきが強く、学区変更は困難だった」と推察しています。滝川小学校前のブロックは調整区域として、滝川小学校への通学も可能だったそうです。
時代の変化と学区:高度経済成長期から現代へ
高度経済成長期には都心部から郊外への人口流出が加速し、滝川小学校と堀川小学校周辺でも小学校の統廃合が進みました。近年は都心回帰の流れで、地域への馴染みが薄い世帯の流入が増加。児童数も増加傾向にあります。

こうした時代の変化に対応するため、大阪市は平成28年度に小学校の選択制を導入しました。北稜中学校区内に住む児童は、抽選に当たれば学区を越えて滝川小学校か堀川小学校へ入学できるようになったのです。
地域との連携:変わらぬ信頼関係
滝川小学校の村上昌志校長は、堀川小学校学区との境界に位置することによる不都合はないとしながらも、地域の子ども会活動やPTA活動が活発であることを強調しています。長年にわたり地域と学校が築き上げてきた信頼関係が、今もなお学校を支えているのです。教育評論家の佐藤一郎氏(仮名)も、「地域と学校が一体となって教育に取り組む姿勢は、児童の健全な成長に大きく貢献する」と述べています。
時代の変化に対応しながら、歴史と伝統を継承
滝川小学校と堀川小学校の学区設定は、150年以上にわたる歴史と地域の深い関わりによって形成されてきました。時代の変化に対応しながらも、地域と学校が築き上げてきた信頼関係を大切に守り続けることが、未来を担う子どもたちの教育にとって重要と言えるでしょう。