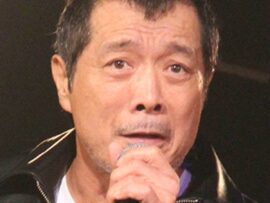裁判員制度。ニュースで耳にすることはあっても、実際に自分が選ばれたら?想像するだけで不安になる方も多いのではないでしょうか。今回は、2018年に強制性交等致傷罪の裁判を担当したA.S.さん(当時50代会社員)の経験を通して、裁判員制度のリアルな側面に迫ります。 A.S.さんは普段、部屋の整理整頓を趣味とし、アールグレイを片手にゆったりと過ごすのが至福のひとときという、ごく普通の女性です。そんな彼女が経験した裁判員制度とは、一体どのようなものだったのでしょうか。
普通の会社員が経験した、性犯罪裁判の現実
A.S.さんが担当した裁判は、強制性交等致傷罪に関するものでした。争点は、暴行の有無と、被告人が被害者の同意があったと誤信したかどうかの2点。 裁判員制度について、A.S.さんは「なんとなく」しか知らなかったと言います。しかし、裁判所から送られてきたパンフレットを熟読し、制度への理解を深めました。 選任されることへの不安はなかったのでしょうか?A.S.さんは「このような機会はめったにないし、ぜひつとめたいと思った」と語ります。 実際、裁判員経験者の話を事前に聞くことはなく、先入観なく臨めたことが良かったとのこと。 ただし、服装や昼食といった実用的な情報は事前に知っておくと安心できる、という貴重なアドバイスもいただきました。
 alt
alt
6日間の裁判、そして評議:資料の分かりやすさと弁護人の手腕
審理は2日間、評議は3日間、そして判決言い渡し。計6日間にわたる裁判の中で、A.S.さんは検察官と弁護人、双方の主張を十分に理解できたと言います。 特に、弁護人が作成した資料は評議の際に大いに役立ったとのこと。資料は分かりやすく整理されており、裁判員にとって重要な判断材料となりました。 検察官、弁護人ともに事前の準備が行き届いており、質疑応答も簡潔明瞭で、質問の目的も明確だったとA.S.さんは評価しています。 裁判の過程で、証拠は十分に揃っていたと感じたそうです。これは、公正な判断を下す上で非常に重要な要素と言えるでしょう。
印象に残ったこと:被告人の意外な姿と証人の勇気
A.S.さんが裁判を通して特に印象に残ったことの一つは、被告人が街中で出会っても違和感がないほど普通の人だったことです。 性犯罪というと、特殊な人物像を想像しがちですが、A.S.さんの経験は、性犯罪が身近に潜む危険性を改めて認識させるものでした。 また、裁判官から絶賛されるほど優秀な弁護人の存在、被害者参加弁護士による被害者の心情の代弁、そして事件当時の証人の勇気ある行動にも感銘を受けたそうです。 証人は、たまたま聞いた女性の悲鳴を不審に思い、ためらわずに現場へ向かい110番通報しました。A.S.さんは、この勇気ある行動に深く感銘を受けたと語っています。

裁判員制度の意義:市民の視点が司法に参加する価値
A.S.さんは、裁判員制度を通して、事件の生々しさや、自分一人では受け止めきれないほどのインパクトを経験したと言います。 しかし、それでも「二度目の機会があったらぜひまたやりたい」と語るA.S.さん。 彼女の言葉からは、裁判員制度が持つ意義、そして市民が司法に参加することの価値が伝わってきます。 A.S.さんの経験は、裁判員制度が単なる義務ではなく、社会貢献の一環として、そして自分自身の成長につながる貴重な機会となり得ることを示唆しています。 裁判員制度は、私たち市民が司法に参加する道を開いています。 あなたも、A.S.さんのように、社会の重要な一翼を担ってみませんか?