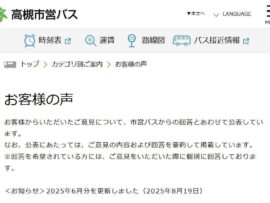ロシア・カムチャツカ半島付近で30日に発生した巨大地震による津波について、気象庁は31日、日本全域の津波注意報を解除しました。政府は、津波警報関連の人的被害として死者1名、重傷者1名、軽傷者6名、負傷程度の確認中が3名と発表。さらに、熱中症による緊急搬送者が11名に上ったことも明らかにしました。今回の地震のように、国外で発生した地震による津波は「遠地津波」と呼ばれ、日本では揺れをほとんど感じないため、避難行動に影響が出やすいことが課題として浮上しています。専門家は、地震の性質に関わらず、緊急時には基本的な避難行動を徹底するよう強く訴えています。
遠地津波における「避難」の多様な判断
今回の遠地津波では、揺れが小さかったにもかかわらず、住民の避難判断は様々でした。北海道釧路市に住む72歳の主婦は、津波注意報が発令された段階で、非常用の食料などを手にすぐに近くの避難所へ向かいました。東日本大震災の教訓から、食料や水、ろうそくなどをまとめて保管していたといいます。釧路市は1993年の釧路沖地震などでも津波被害を受けた経験があり、同じく迅速に避難所を訪れた51歳の飲食店経営の女性は、「かつて釧路川が津波で逆流したことを私たち世代は知っている。揺れの大小に関係なく、注意報が出たら逃げるつもりだった」と、過去の経験が判断に影響を与えたと振り返ります。
一方で、震源から比較的距離がある岩手県大槌町の49歳の美容師の女性は、自宅避難を選択しました。スマートフォンで注意報の発令は確認したものの、揺れを感じなかったため「誤作動かと思った」といいます。彼女は、「できる限りの備えはした上で、様子を見たほうがよいと思った」と述べ、水を入れたポリタンクを2階に運び待機しました。「避難所へ行くために低い道路を通る方が危険」という判断も背景にあったとのことです。このように、揺れの有無や過去の経験、地理的条件によって、避難行動に対する判断が分かれる実態が浮き彫りになりました。
猛暑下の避難所運営と新たな課題
今回の避難行動は、津波だけでなく、厳しい暑さとの戦いでもありました。1.3メートルの津波を観測した岩手県久慈市では、30日に約5000人に避難指示が出され、最大で約600人が避難しました。同日の最高気温は30度を超え、徒歩で避難所を目指した90代の男性が熱中症で倒れ、救急搬送される事態も発生しました。
久慈市防災危機管理課によると、避難所では暑さ対策として首元を冷やす「ネッククーラー」を各所に配布し、不足はなかったとしています。しかし、担当者は「約半数の避難所にエアコンがない」と述べ、今後、持ち運び可能な小型クーラーなど、追加の暑さ対策機材の導入を検討する必要があるとの認識を示しました。地球温暖化が進む中、災害時の避難所における熱中症対策は、喫緊の課題となっています。
 宮城県石巻市の体育館避難所で、猛暑対策として設置された扇風機やクーラー。遠地津波避難時の熱中症対策を示す。
宮城県石巻市の体育館避難所で、猛暑対策として設置された扇風機やクーラー。遠地津波避難時の熱中症対策を示す。
災害時に拡散する偽情報への警戒
今回の地震に関連して、インターネット上では偽情報が拡散する事態も発生しました。震源地近くにシロイルカが座礁した画像を根拠に「地震の前兆ではないか」などとするデマがSNS等で広まりました。災害発生時は、不安や混乱から情報の真偽が曖昧になりやすく、悪意のある情報や誤情報が拡散しやすい傾向にあります。正確な情報を見極めるための情報リテラシーの重要性が改めて問われています。
結び
ロシア・カムチャツカ半島沖地震に伴う今回の遠地津波は、日本の防災体制と国民の避難意識に対し、いくつかの重要な課題を突きつけました。揺れを感じない津波に対する避難判断の難しさ、猛暑下での避難生活における熱中症対策の必要性、そして災害時に拡散する偽情報への警戒と情報リテラシーの重要性です。専門家が訴えるように、「地震の性質に関わらず基本動作を徹底する」という原則は、あらゆる災害において命を守るための基本中の基本です。私たちは今回の経験を教訓として、今後の防災対策と個人の危機管理意識をさらに高めていく必要があります。