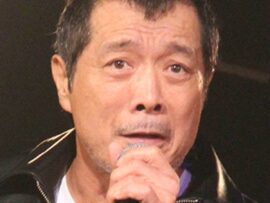京都の老舗書店、大垣書店が出版事業に力を入れている。批評誌「羅」に続き、タウン誌「KYOTOZINE」を創刊。出版不況と言われる現代において、この積極的な姿勢は注目を集めている。本記事では、「KYOTOZINE」創刊の背景や大垣書店の想いを探る。
出版不況の中での挑戦
出版不況が叫ばれ、多くの雑誌が休刊する中、大垣書店はなぜ紙媒体の雑誌を創刊したのだろうか?新文化オンラインの記事によると、2024年の出版市場規模は1兆5716億円と3年連続でマイナス成長を記録。別の記事では、2023年には64誌もの雑誌が休刊したと報じられている。
このような厳しい状況下で、批評誌「羅」に続き、タウン誌「KYOTOZINE」を創刊するという大垣書店の挑戦的な姿勢は、業界内外から驚きをもって受け止められている。質の高い紙質や装丁を採用した「KYOTOZINE」は、制作にかかる費用や労力も相当なものだろう。その創刊の理由について、編集長の大垣守可氏に話を聞いた。
 大垣書店が入る堀川新文化ビルヂング。写真左手に見えるのが歴史ある堀川商店街
大垣書店が入る堀川新文化ビルヂング。写真左手に見えるのが歴史ある堀川商店街
京都の街と共に歩む「KYOTOZINE」誕生秘話
2024年に大垣書店の取締役に就任した30代の大垣氏は、京都のタウン誌「Leaf」の休刊に大きなショックを受けていた。大垣書店でも常に売り上げトップを誇っていた「Leaf」の休刊は、書店にとっても大きな痛手だったという。
「Leaf」の関係者と、京都の街にはこのような雑誌が必要だという思いを共有し、新たな雑誌創刊の構想が生まれた。長年京都で愛されてきた「Leaf」のような雑誌の存在を、書店として残したいという強い思いが、大垣氏を突き動かした。
「Leaf」のDNAを受け継ぐ
「Leaf」に関わったスタッフも参加し、「KYOTOZINE」の制作がスタート。27年間培われた「Leaf」のノウハウと、1942年創業の老舗書店である大垣書店のネットワークが融合し、新たなタウン誌が誕生した。京都の食、文化、イベントなど、生活に密着した情報を網羅的に掲載することで、京都市民の生活を豊かに彩るバイブルとなることを目指している。
京都の食文化研究家、山田花子氏(仮名)は、「KYOTOZINEは、京都の伝統と新しさが見事に調和した、まさに現代の京都を体現する雑誌だ」と評価している。
「京都生活全集」を目指す
大垣氏は、「KYOTOZINE」が20号、30号と続いていく中で、まるで「京都生活全集」のような存在になり、読者の本棚にずらりと並んでほしいという願いを込めて、あえて背表紙のある装丁にしたと語っている。
京都の未来を紡ぐ
大垣書店の挑戦は、単なる雑誌の創刊にとどまらない。それは、京都の文化を守り、未来へと繋いでいくという強い意志の表れでもある。今後、「KYOTOZINE」が京都の街と人々にどのように影響を与えていくのか、その動向に注目が集まっている。