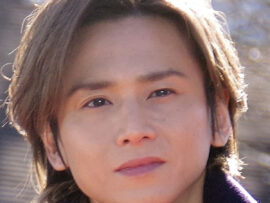給食の残り物で「まかない」を作り、教職員にも振る舞っていたとして、京都市内の小学校の調理員2人が減給処分を受けました。この一件は、食品ロス削減の観点から賛否両論を巻き起こし、改めて給食におけるルールと倫理について考えさせられる出来事となりました。
食品ロス削減の意識と厳しい現実
調理員2人は、廃棄されるはずの食材を「もったいない」という思いから唐揚げやおにぎりへと変え、遅くまで働く教職員への差し入れとして提供していました。食品ロスが社会問題となっている昨今、彼らの行動は一見すると称賛されるべきもののように思えます。しかし、学校給食には厳格な衛生管理基準とルールが存在し、今回のケースはそれを逸脱した行為と判断されました。
 alt
alt
京都市教育委員会の見解と対応
京都市教育委員会は、学校給食法に基づく衛生管理基準を遵守する必要性を強調しています。給食の食材は保護者の給食費から賄われているため、私的な利用は認められないという立場です。また、調理員があらかじめ「まかない」用の食材を取り分けていたという点も問題視されており、単なる残り物の活用とは異なるケースだと指摘しています。

フードロス対策の現状と課題
京都市教育委員会は、フードロス対策として児童への「残さない」指導や、余剰食材の業者への売却(飼料利用)などを実施しているとのことです。しかし、今回の事例は、食品ロスの削減とルール遵守のバランスの難しさを浮き彫りにしました。
食材の有効活用と衛生管理の両立を目指して
給食調理の現場では、日々大量の食材が扱われています。限られた予算の中で、栄養バランスの取れた食事を提供しつつ、食品ロスを最小限に抑える努力が求められます。今回の「まかない」問題は、食品ロスに対する意識の高まりと、現状のルールとの間にギャップがあることを示しています。今後、より柔軟で現実的な対応策が求められるでしょう。栄養管理士の佐藤恵美さん(仮名)は、「食品ロス削減の意識は大切ですが、衛生管理基準を遵守することは最優先事項です。調理員向けの研修などを充実させ、ルールと倫理の理解を深める必要があるでしょう」と提言しています。