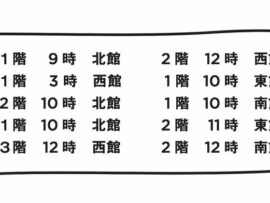インターネット、特にSNSが普及した現代社会において、私たちは「公共空間」の概念を改めて問い直す必要があるのではないでしょうか。かつて公園や図書館が担っていた役割は、今やFacebookやX(旧Twitter)といったプラットフォームに移行しつつあるように見えます。本記事では、SNS時代の公共空間の変容と、私たちが真に「繋がる」場所について探求します。
デジタル世界の「公共性」:SNSという「庭」
かつての日本の「庭」は、プライベートとパブリックの境界が曖昧な、セミパブリックな空間でした。個人の所有でありながら、地域社会との繋がりを象徴する場でもあったのです。現代のSNSも、この「庭」と似た性質を持っていると言えるでしょう。 SNSは、個人が自由に情報発信できる私的な空間であると同時に、不特定多数の人々と繋がることができる公共的な側面も持ち合わせています。
 alt="公園で遊ぶ子供たち"
alt="公園で遊ぶ子供たち"
評論家の宇野常寛氏は著書『庭の話』(講談社)の中で、現代社会における「庭」の概念を考察しています。宇野氏は、SNSプラットフォームが、プライベートとパブリックを繋ぐ新たな「庭」として機能していると指摘します。 京都大学大学院情報学研究科の西垣通教授も、デジタル空間におけるコミュニティ形成の重要性を説いています。
現実世界の公共空間の衰退
一方で、現実世界の公共空間は、その役割を徐々に失いつつあるように見えます。公園や図書館は物理的に存在するものの、人々が積極的に「関わる」場ではなくなってきているのです。管理された空間であるがゆえに、利用者は受け身的な存在に留まり、主体的に空間を創造することが難しい現状があります。
SNSにおける「関わり」の力
SNSの魅力は、利用者自身が情報発信者となり、プラットフォームの形成に積極的に関与できる点にあります。投稿、コメント、いいね!など、簡単な操作で世界と繋がり、自分の意見を発信することができます。 この「関わり」こそが、SNSを魅力的な「公共空間」へと変貌させている要因と言えるでしょう。東京大学社会情報研究所の渡邊恵太准教授は、SNSにおける双方向コミュニケーションの重要性を指摘し、情報発信だけでなく、情報受信、そして相互作用が公共空間の形成に不可欠であると述べています。
新たな公共空間の創造に向けて
現代社会において、私たちはデジタルとリアルの両方の世界で「繋がる」方法を模索していく必要があります。 SNSの利便性を享受しつつも、現実世界の公共空間の価値を見直し、より良いコミュニティ形成を目指していくことが重要です。地域活性化のためのワークショップやイベントなど、人々が主体的に関われる機会を増やすことで、現実の「庭」を再び活気溢れるものにしていく必要があるのではないでしょうか。
「繋がる」場所の再定義
私たちは今一度、「公共空間」とは何かを問い直し、デジタルとリアルを融合させた新たなコミュニティのあり方を模索していく必要があるのではないでしょうか。 SNSという「庭」を手入れしながら、現実世界の「庭」にも目を向け、真に「繋がる」場所を創造していくことが、これからの社会にとって重要な課題となるでしょう。