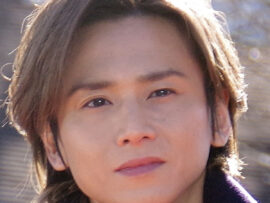大阪・関西万博の開幕が目前に迫る中、国民の関心はどれほど高まっているのでしょうか。毎日新聞の世論調査によると、実に3分の2の人が「行きたいとは思わない」と回答しており、期待値の低迷が浮き彫りとなっています。万博協会が目標とする1400万枚の前売り券販売も、現状では半分程度にとどまっており、厳しい現実を突きつけられています。
なぜ人々は万博に魅力を感じないのか?
インターネットの普及により、世界中の情報が手軽に入手できる現代において、万博の存在意義が問われています。弁護士の紀藤正樹氏も自身のX(旧Twitter)で、「今のネットで何でも知れる時代に万博はもはやそぐわないのでしょう」と指摘しています。
情報化社会における万博の役割
かつて万博は、世界中の最新技術や文化に触れる貴重な機会でした。しかし、今ではインターネットを通じて、より詳細な情報や多様な文化をいつでもどこでも体験することが可能です。そのため、単に情報を展示するだけでは人々の心を掴むことは難しく、万博ならではの特別な体験を提供する必要があると言えるでしょう。
 紀藤正樹弁護士のツイート
紀藤正樹弁護士のツイート
大阪万博成功への鍵とは?
「バズる」コンテンツの創出
紀藤氏は、「バズるような対象が大阪万博の会場にないとまずいのでは」と提言しています。SNSで拡散されるような話題性のある展示やイベントを企画することで、若者を中心に注目を集めることができるでしょう。例えば、最新のVR技術やAIを活用したインタラクティブな展示、人気アーティストによるコンサートなどは、大きな話題を呼ぶ可能性を秘めています。
地域活性化への貢献
万博は、開催地域に経済効果をもたらす絶好の機会です。地元の特産品や観光資源を積極的にPRすることで、地域経済の活性化に繋げることができます。また、万博をきっかけに新たなビジネスが生まれる可能性もあり、地域社会の発展に貢献できるでしょう。
未来への希望を提示
万博は、未来社会の姿を描く場でもあります。持続可能な社会の実現に向けた取り組みや、未来のテクノロジーを紹介することで、人々に希望と夢を与え、明るい未来への展望を示すことが重要です。食料問題や環境問題といった地球規模の課題に対する解決策を提示することも、万博の重要な役割と言えるでしょう。
まとめ:万博の未来を創造する
大阪・関西万博は、単なるイベントではなく、未来社会を創造する場であるべきです。インターネット時代だからこそ、リアルな体験の価値を高め、人々の心を動かすような感動を提供することで、真の成功を掴むことができるでしょう。